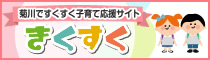ホーム > 市政情報 > ”旬感”まちのニュース > 2025年度 > 令和7年7月まちの話題を紹介します
ここから本文です。
更新日:2025年8月4日
7月30日(水曜日)「よるのとしょかんおはなし会」が開催されました
7月30日、小笠図書館で「よるのとしょかんおはなし会」が初めて開催されました。
このイベントは、夏休みに夜の図書館で特別な思い出を作ってもらうとともに、図書館や読書への親しみを深めてもらうことを目的としたもので、親子9組25人が参加しました。
当日は、小笠図書館の職員が以下の4冊を朗読しました。
1.『わにわにのおでかけ(文/小風さち、絵/山口マオ)』
2.『おめんです(作・絵/いしかわこうじ)』
3.『かっぱ(作/杉山亮絵、絵/軽部武宏)』
4.『めっきらもっきらどおんどん(作/長谷川摂子、画/ふりやなな)』
『おめんです』はしかけ絵本になっています。「○○のおめんをかぶっているのだあれ?」と職員が問いかけると、参加したこどもたちは、次々に自分の答えを発表。職員がしかけを動かしてお面を外し、答えの動物が現れると、子どもたちからは歓声があがりました。
『かっぱ』は、日本の妖怪・河童が登場するお話。少し怖い絵柄で、怒った河童が人間を沼に引きずり込もうとする場面では、子どもたちはハラハラしながらも、真剣な表情で物語に惹き込まれていました。
『めっきらもっきらどおんどん』は、少年が迷い込んだ不思議な世界でのでき事を描いた絵本。子どもたちは、幻想的な世界にわくわくしたり不安になったりする少年と同じ気持ちになりながら、物語の冒険を楽しんでいました。絵本の朗読が終わると、職員が絵本の内容についてクイズを出題。子どもたちは一喜一憂しながらクイズに挑戦しました。
最後には、童謡「おばけなんてないさ」をみんなで歌って、会を締めくくりました。
参加した子どもは、「夜の図書館はいつもと雰囲気が違ってドキドキしたけど、どのお話も楽しかったです。また同じようなイベントがあったら参加したいです」と話しました。



7月29日(火曜日)「夏休みみんなで宿題やる会」が開催されました
7月29日、平川コミュニティ防災センターで「夏休みの宿題をみんなでやる会」が実施されました。親が共働きなどの理由で家にいる子どもたちに交流の機会を与えることを目的に、青少年健全育成平川支部が毎年夏休みと冬休みに実施している恒例行事。今回、平川地区や嶺田地区の小学生27人が、同支部のメンバーや「地域のためなら」と協力をしてくれた中学生ボランティア23人と夏休みの宿題をしました。
参加した児童は、夏休みの宿題に集中して取り組み、分からない問題がある人は、同支部のメンバーやボランティアの中学生に教えてもらいながら問題を解いていきました。
参加した6年女子児童は、「中学生が分かりやすく教えてくれて宿題がはかどりました。お盆には、家族旅行に行くので、その前に宿題を終わらせたいです」と嬉しそうな様子で話してくれました。ボランティアの女子中学生は、「小学生がしっかりと話しを聞いてくれて嬉しかったです。機会があったらまた、参加したいです」と話しました。



7月26日(土曜日)生活環境フェスタ2025が開催されました
7月26日、文化会館アエルで生活環境フェスタが開催されました。生活環境を良い状態に保つためには何をすればいいかを楽しく学んでもらい、環境問題への関心を高めることが目的。家族連れなどおよそ1,200人が訪れ、身近な生活環境に関するさまざまな展示や体験コーナーで、環境保全の大切さを楽しみながら学びました。
下水道課のコーナーでは、マンホールポンプや下水道管点検ロボットの操作実演、浄化槽模型などが展示され、普段はなかなかみることができない展示に、訪れた人は興味津々でした。また、菊川市や近隣市町のマンホールのふたが並べられ、訪れた人が写真を撮るなどして賑いました。
環境推進課のコーナーでは、魚釣りゲームが行われました。もし、このまま海がごみなどで汚された場合に、どうなってしまうかを遊びながら学べるもので、子どもたちは、魚だと思って釣り上げたものが実はごみだったという結果に、驚いていました。
さらに、同時開催した「パワフル・ジャンプきくがわinアエル」との共同スタンプラリーに参加し、スタンプを埋めた人には景品がプレゼントされました。



7月26日(土曜日)~15日(月・祝)ひらかわ会館夏休み企画「こども昆虫展」が開催されています
7月26日から28日まで、ひらかわ会館でカブトムシなどの生き物を間近に観察できる「ひらかわ会館こども昆虫展」が開かれています。平川地区コミュニティ協議会の主催で毎年多くの親子連れが訪れる恒例行事。
会場には、高さ2m、長さ6mほどの特設小屋が設置され、中に入った子どもたちは、放し飼いにされたおよそ100匹のカブト虫と自由に触れ合っていました。また、世界の珍しいカブトムシやクワガタなどが展示され、ボランティアの学生や協議会の会員が、観察する子どもたちに昆虫の解説をしていました。
また今年は、「昆虫の進化」をテーマに展示も実施。手作りの模型やパネルなどを展示し、子どもたちにわかりやすく昆虫の進化の資料を解説付きで展示していました。
その他、正解者の中から抽選で、景品がもらえる「昆虫クイズ」が行われているほか、最終日には、引換券を持っている人に向けて特設小屋に展示されていたカブト虫の無料配布があります。身近な自然に生息する生き物との触れ合いを、ぜひお楽しみください。



7月23日(水曜日)親子スポーツ教室にてジュビロ磐田によるサッカー教室が開催されました
7月23日、小笠体育館にて、株式会社ジュビロが講師を務める「親子サッカー教室」が開催されました。この教室は、親子で様々なスポーツを体感し、スポーツの楽しさを感じてもらうとともに、親子で過ごす時間を増やし、信頼関係を深めることを目的に開催している「親子スポーツ教室」の一環。7月16日から8月13日まで全5回の日程で開催されている中の第2回目の開催となります。
ジュビロ磐田と菊川市は、ジュビロ磐田がJリーグ昇格30周年を迎えた令和5年5月にホームタウンへ加盟。以来、地域活性化やスポーツ振興といった地域貢献活動を積極的に行っています。また、市と健康増進に関する連携協定を締結している明治安田生命保険相互会社の協力を得て、Jリーグのサポーターであるといったご縁から、親子スポーツ教室に講師として参加いただきました。
当日は、市内在住の年中児から小学校3年生以下の児童とその保護者20組47人が参加。親子で汗を流しながら楽しいひとときを過ごしました。
プログラムは、まずボールに慣れるところからスタート。親子でボールを奪い合ったり、ドリブルをしたりと、ボールに触れる楽しさを体感しました。
続いてシュート練習では、子どもたちが保護者からパスを受け取り、ゴールに向かってボールを蹴る練習を行いました。コーチは「足元でしっかりボールを止めて、思い切りゴールに向かって蹴ること」とアドバイス。アドバイスに従ってシュートを決めると、親子でハイタッチを交わす姿が見られました。
最後には10人程度ずつに分かれて試合が行われました。親子混合のチーム編成で、子どもたちは大人に負けず、必死でボールを追いかけ、ゴールを狙っていました。ゴールが決まるとチームメンバー同士で喜びを分かち合いました。
最後には、2組に分かれて試合が行われ、子どもと親が混合したチームでプレーしました。子どもたちは、大人たちに負けまいと必死でボールを追いかけ、ゴールを目指しました。ゴールが決まると、チームメンバー同士で喜びを分かち合いました。



7月22日(火曜日)シニアクラブ菊川交通教室が行われました
7月22日、ひらかわ会館でシニアクラブ菊川交通教室が行われました。シニアクラブ菊川は、60歳以上の会員が集まり各種事業を実施しながら会員の親睦を深める組織です。今回、各種事業の一つとして実施された交通教室では、クラブ会員およそ40人が交通安全協会菊川支部の交通指導員から「事故にあわない・起こさない」ためのポイントやトレーニング方法を学びました。
参加者ははじめに、「座学」として指導員からスライドを使って事故の現状や交通ルールを再確認しました。県内で起こった交通事故による死亡者数のおよそ6割が高齢者。普段やってしまいがちな横断歩道の渡り方や、一旦停止の止まり方などの“良くない例”の動画を見ながら指導員は、「交通ルールは十分皆さんご存知だと思いますが、ルールが自己流になっていたり、雑になっていたりしませんか?」と問いかけ、「事故にあわない・起こさないために、日頃の自分の行動を振り返ってみてください」とお願いしました。その他、交通事故を防ぐうえで重要となる動体視力を簡単に鍛えるトレーニング方法などを紹介。参加者は、一緒に手を動かしながら実践していました。また座学の後には、3つの機械をそれぞれ体験しながら俊敏性をチェック。参加者は自分の身体能力や気質を把握することができました。
参加した会員は「運転中はルールに気を付けているつもりだったが、身体能力のチェックで自分がせっかちだと知った。今後は自分の気質を踏まえて、安全運転していきたい」と話しました。



7月19日(土曜日)田んぼアート菊川ライトアップ鑑賞会が開催されました
7月19日、下内田の田んぼアート会場でライトアップ鑑賞会が行われました。あたりが薄暗くなると、やぐらからは照明が当てられ、夜の闇にアートが浮かび上がりました。
また、水田に向う川沿いの通路では、袋井太鼓による演奏や竹灯籠も並べられ、訪れた人は模様を眺めたり、写真を撮ったりして幻想的な雰囲気を楽しみました。
ライトアップは、本日7月20日(日曜日)も大鑑賞会に合わせて9時まで開催されています。ぜひ、普段とは違う幻想的な田んぼアートをご覧ください♪



7月18日(金曜日)六郷小学校で「戦争体験を聞く会」が開催されました
7月18日、六郷小学校で「戦争体験を聞く会」が開催されました。国語の読み物教材である『平和のとりでを築く』や、社会科の歴史の学習に結びつけ、児童たちの戦争に関する理解を深めることを目的としています。今回は、「戦争体験を伝える会」の北原勤さんを講師に迎え、北原さんが幼少期より伝え聞いてきた市内の戦争体験を聞きました。
北原さんはまず、戦時中に牧之原台地に「大井海軍航空隊」というパイロット訓練用の飛行場(海軍基地)が設置されていたことを説明しました。そして、1945年7月28日から30日にかけてアメリカ軍の空襲を受け、基地が壊滅的な状況となった様子を、当時の記録(藤枝防空監視哨関係文書)を基に読み解きました。
さらに、大井海軍航空隊への空襲で菊川市(当時の小笠町)の古谷・丹野地区におよそ50個のM83爆弾が300メートル範囲に投下され、死亡者が8人(即死6人、負傷後死亡2人)、負傷者が4人に上ったことを説明。M83爆弾は、その形から「缶詰爆弾」とも呼ばれており、落下してきた爆弾を見に行った人々が爆発に巻き込まれたことが語られました。亡くなった人の中には、今回話を聞いた児童と同じ年齢の子どももいたことが明かされ、児童たちは真剣な表情で北原さんの話に耳を傾けました。
その後、北原さんが持参した実際の缶詰爆弾を見せてもらうと、児童たちは「こんな小さいもので人の命が奪われるのか」と驚きの声を上げていました。
北原さんの話を聞いた児童たちは、戦時中は“死”が隣り合わせな状況であったことを体感し、菊川市にも戦争の爪痕があることを学びました。また、今回の貴重な経験を通じて、現代に生きる自分たちにとっても、戦争は遠い世界のでき事ではないことを改めて認識し、平和に対して自分自身の考えを持つきっかけとなりました。



7月18日(金曜日)小笠北小でひまわりが咲き始めました
7月18日、小笠北小学校で3年生が植えたヒマワリの花が咲き始めました。「フラワーパワー大作戦」と題し、地域ボランティアの塚本隆男さんと一緒に花の力でみんなに元気を届けようと実施している取り組み。花は4月に同校3年生60人が、塚本さんに種のまき方を教わりながら、ヒマワリやコスモスの種を校庭の花壇に蒔きました。
植えたヒマワリは10種類以上。よく見ると、花びらの形や中央部分の色が違っています。
児童は、嬉しそうにきれいに咲いた花を見ていました。
ヒマワリは夏休み明けに、理科の授業で花の観察に使用される予定です。



7月17日(木曜日)内田小学校児童と小谷小学校児童の交流会が開催されました
7月17日、市と友好都市協定を結んでいる長野県小谷村の小谷小学校5年生16人が、菊川市を訪れ、内田小学校5年生23人と交流しました。両校児童は、6月に実施した2回のオンライン会議で、互いの意見を出し合い、交流内容を企画。今回の対面交流では、事前に顔を合わせていることから、緊張感なく温かな交流を行いました。
交流会では、初めに、内田小の代表児童が歓迎のあいさつをしました。続いて、両校児童が事前に自分で作った名刺を全員と交換。児童は、自分の名前を言いながら「よろしくお願いします」と笑顔で交換していました。その後、両校代表児童が、スクリーンを使って、事前に用意した映像に説明を交えながら自分たちの学校について紹介。また、内田小が企画した、校舎内のさまざまな場所を巡りながらスタンプを集めるスタンプラリーや、小谷小が企画した、フルーツバスケットのルールを応用した遊び「なんでもバスケット」が行われ、両校児童は、互いに交流し、大笑いし合いながら楽しんでいました。
最後には、市公式マスコットキャラクター「きくのん」が登場。「きくのん」から小谷小児童へ深蒸し菊川茶ペットボトルがプレゼントされ、全員で記念撮影をして楽しい交流の時間を締めくくりました。



7月17日(木曜日)「岳洋学舎オリジナルあいさつプロジェクト」が実施されました
7月17日、菊川市内の3つの小学校で「岳洋学舎オリジナルあいさつプロジェクト」が実施されました。このプロジェクトは、地域の人々のつながりが希薄化している現状を踏まえ、子どもたちが主体となってあいさつを通じた交流を行うことで、菊川市を明るく元気なまちにすることを目的としています。
菊川市では、各中学校区において「小・中学校のたての接続」と「学校と地域社会のよこの連携」を基盤とした『菊川市小中一貫教育〜「学びの庭」構想〜』により、学校を核とした地域づくりを目指しています。その中で、岳洋中学校と、小笠北小学校・小笠東小学校・小笠南小学校の3校を「岳洋学舎」と位置づけ、小中一貫教育の理念に基づいた取組を進めています。
今回のプロジェクトでは、岳洋中学校の生徒62人が自主的に学舎内の小学校を訪問。校門前に立ち、登校してくる小学生たちにあいさつを行いました。
小笠南小学校では、その小学校を卒業した16人の岳洋中学校の生徒が参加。小雨が降る中、「みんなであいさつすてきなあいさつ」と書かれたのぼり旗を掲げながら、小学生たちと元気よくあいさつを交わし、岳洋学舎内に明るい笑顔と温かな交流が広がりました。
なお、本プロジェクトは明日7月18日(金曜日)にも実施予定です。



7月15日(火曜日)相談だけで終わらない支援が初実現!EnGAWA5(ご)はんの日
7月15日、産業支援支援センターEnGAWAで5(ご)はんの日が開催されました。同施設で5の付く日に開催されている「5(ご)はんの日」では、お昼の時間に地元や近隣市町のお店が日替わりでお弁当を販売。同施設へ気軽に足を運んでもらうため、また、菊川市で認知・販路拡大を目指す事業者を応援するために企画されたイベントです。
昨年6月から開催されている同イベントですが、今回初めて、産業支援センターで創業支援を行った事業者が出店しました。出店したのは、掛川市で今年の2月にお店を構えた「Love∞Spice(らぶむげんすぱいす)」。同施設の利用者や来訪者にタコライス風のオーガニックハーブ入りキーマカレーを販売しました。お弁当を買いに訪れた人は、イベント期間中に無料開放されているコワーキングスペースで、仲間と一緒にお話をしながら食事を楽しんだり、仕事の合間にじっくり味わったりと、それぞれにイベントを楽しんでいました。
今回の出店者である中村浩子(ひろこ)さんは、福祉に携わる仕事をする中で「誰もがホッとできる居場所を作りたい」と開業を決意。初めての開業を目指す中で、金融機関から産業支援センターで実施している無料相談の紹介を受け利用を始めました。中村さんは、「開業に至るまでの道のりがほとんどわからなかったので、無料相談では必要な手続きなど細かいところから一つ一つ丁寧に教えてもらいました。今日のイベントでは、このお店を初めて知ってもらえる人にPRできてよかったです。より多くの人に知ってもらい、居場所を必要としている人に、このお店があるということが届けばうれしいです」と話しました。



7月11日(金曜日)外国人の子どもたちが流しソーメン&スイカで日本の文化を体験
7月11日、平川コミュニティ防災センターで外国籍の児童が日本の夏の風物詩を体験しました。
市では、社会と行政がそれぞれの役割と責任を担いつつ相互に協力しあう、「地域の青少年は地域で守り育てる」を柱とした事業を推進しています。そのことから青少年健全育成市民会議平川支部では、地区住民に外国籍の方が多いため、多文化共生に力を入れていて、夏と冬の年2回、日本の伝統的行事を毎年開催。今回は、市内の外国人の子どもの就学施設「虹の架け橋」の児童28人と高橋地内に子どもの居場所づくりとして開設している「こどもの文化センター」の幼児1人や先生たちが、同支部のメンバーと流しソーメンとスイカ割りを楽しみました。
はじめに、子どもたちは夏の風物詩の流しソーメンを体験。同支部メンバーがこの日のために手作りした竹桶に水と一緒にソーメンを流すと、児童は上手に箸を使ってすくい、おいしそうに食べていました。
また、スイカ割りでは棒を勢いよく振り下ろし、見事にスイカが割れると、周囲から大きな歓声が沸き上がりました。割ったスイカは、地域の女性ボランティアにより三角形に切り分けられ、参加者全員で仲良く食べました。はじめてスイカを食べた児童は「おいしい」と話し、何切れも手に取って食べていました。
日本の夏の風物詩を体験した中学2年生の男子生徒は、「ソーメンつゆは酸っぱく感じたけどおいしかった!スイカおいしい!またやりたい」と話し、満喫した様子でした。
同支部の黒田潔(きよし)支部長は、「母国の文化も大切にしてもらいながら、日本の文化にも触れてくれたらうれしいです」と話しました。



7月11日(金曜日)病院ボランティア“星”への感謝状贈呈式が行われました
7月11日、菊川市立総合病院で病院ボランティア“星”への感謝状贈呈式が行われました。
同ボランティアは、昭和61年10月に発足し、毎月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の午前8時30分から10時30分まで、受診患者への院内の案内、診療申込書などの代筆、乳幼児の子守り、車椅子患者の介助などのボランティア活動を行っています。今回は、同病院を受診する患者にとってより良い病院となってほしいという思いからへ寄附をいただきました。
贈呈式では、同ボランティアのメンバーから松本有司院長へ寄附金が手渡され、松本有司院長からは感謝状が贈られました。贈呈された寄附金は、同院で不足している血圧計の補充に活用される予定です。
松本有司院長は、「日々患者様に寄り添い活動していただき大変感謝しています」と感謝の言葉を伝えました。
ボランティアメンバーは、「これからも患者目線で病院を見つめ、病院が患者にとって良い方向へ向かうよう改善点も提案していきたいです」と話しました。



7月10日(木曜日)コンテンポラリーダンスワークショップ「細胞レベルでつながるダンス!」が開催されました
7月10日、文化会館アエルでダンスワークショップ「細胞レベルでつながるダンス!」が開催されました。このイベントは、令和5年度より実施している「公共ホール現代ダンス活性化事業」の一環で、コンテンポラリーダンスを通じて公共ホールの活用と地域の活性化を目的として行われています。今年で3年目の開催となる本事業では、身体表現の楽しさや奥深さを体験できることを目指しています。
当日は、振付師でありダンサーでもある井田亜彩美さんを講師に迎え、17人が参加しました。
初めに、身体を大きく動かし、ゆっくりほぐす準備運動からスタート。次に、「掃除する」「洗濯する」といった日常の動きや、「動物の動きを模倣する」といったテーマで自由に表現して踊りました。また、「リズムに合わせてペアで簡単な振り付けを踊る」、「目をつぶった相手を支えて身体を動かす」など、参加者同士が触れ合いながら身体を動かし、空気を感じる体験をしました。
初対面の人もいる中で、参加者は、最初は緊張した様子でしたが、徐々に笑顔が増え、交流の輪が広がりました。ワークショップの終盤には、参加者同士で自然なハイタッチが交わされ、ダンスを通じて楽しい時間を共有しました。
ワークショップ終了後、参加者からは、「参加者のみんなとたくさん触れ合いながらダンスができて、想像以上に楽しかった」、「初対面の人と一緒に踊るのは、最初は恥ずかしかったが、ワークショップを通じて仲良くなり、楽しく踊ることができた」、「ダンスの表現方法は無限だと実感した。今日の体験を通じて美しい世界が見えた」と話しました。
講師の井田さんは、「参加者には幅広い年代の方々が集まったので、多様なアプローチを提案しました。皆さんがそれぞれに『楽しい』と感じられる瞬間があったのではないでしょうか。コンテンポラリーダンスは特定のルールに縛られず、自由な発想や身体表現を楽しむダンスです。今回のワークショップをきっかけに、ダンスが身近で誰でも楽しめるものであることを知り、興味を持っていただければ幸いです」と話しました。



7月7日(月曜日)菊川東中学校で「つなげよう和服の文化」の授業が行われました
7月7日、菊川東中学校で「つなげよう和服の文化」の授業が行われました。この授業は、家庭科の授業の一環として行われ、生徒に日本の民族衣装「和服」に関心を持ってもらうことが目的。同校の3年生およそ112人が参加し、各クラスが1~4時間目に分かれて、市内にある着物の仕立て行う浅井工房や呉服店などの地域ボランティアから浴衣の着方やたたみ方を学びました。
3年3組の授業では、はじめに、浅井工房の浅井さんが、「日本の民族衣装である着物の魅力を知って欲しいです。気軽に着られる浴衣の着方をぜひ覚えてください」と伝えました。
次に、生徒は、浴衣を着る体験に挑戦。左側の襟が上になるように着ることや腰ひもの縛り方、男女それぞれの帯の巻き方などを教わりながら、自分で浴衣を着ていきました。着物のたたみ方も教わり、最後に、自分が着た浴衣を畳みました。また、津軽三味線ハレルヤの大塚晴也さんによる、三味線も披露され、生徒は三味線の力強い音に興味津々な表情で聞き入っていました。
浴衣を着てみた女子生徒は、「初めて着たけど着心地がいいです。花火大会に着ていきたいです」と、男子生徒は「帯を結ぶのが難しかった。意外と涼しいと感じました」と話しました。
浅井さんは、「浴衣は、作り直しができ、親から子へ引き継げることも魅力の一つです」と話しました。



7月5日(土曜日)親子読書のつどい「第34回おはなしステーション」が開催されました
7月5日、文化会館アエル大ホールで親子読書のつどい「第34回おはなしステーション」が行われました。市立図書館が、子ども向けに開催している恒例行事で、絵本やおはなしの世界に触れることで、読書や図書館への興味を深めてもらうことが目的のイベント。市内在住の乳幼児から小学校低学年の児童とその家族およそ250人が参加し、菊川吹奏楽団による演奏や、水ようおはなし会、やなぎ文庫による絵本を題材にした人形劇を楽しみました。
はじめに、市内を中心に活動している市民楽団「菊川吹奏楽団」による演奏が披露されました。「さんぽ」、「世界中の子どもたちが」「てのひらを太陽に」では、来場者も一緒に歌いながら演奏を楽しみました。
次に、水ようおはなし会の手作りの人形劇「ももたろう」が上演されました。桃太郎が、犬・猿・雉と一緒に、鬼ヶ島へ鬼退治に向かう際には、「がんばれ、がんばれ、おー!」と掛け声をかけ、来場者みんなで桃太郎を応援しました。来場者の応援のおかけで、鬼を退治し、鬼ヶ島から宝物を持って村に帰ると、おじいさん・おばあさんは大喜び。人形劇が終わると、会場からは大きな拍手が贈られました。
イベント終了後、ホールの出口では、人形劇に登場した人形たちが来場者をお見送りしました。



7月4日(金曜日)小笠高校で「市内で活躍している大人の活動を知ろう」をテーマに講話が行われました
小笠高校1年生では、「人文国際」や「自然科学」など9つの系列ごとに別れ、およそ2カ月間でそのテーマに関して探求し「大人を巻き込む企画」を練る授業が行われています。その先駆けとして7月5日、「市内で活躍している大人の活動を知ろう」と題し、市内で活躍する医療従事者や農業法人、社会福祉法人など、9の企業や団体など講師として講話する授業が行われました。
講師は、「系列:人文国際/講師:NPO法人静岡教育フォーラム」など、系列に合わせて組まれており、同学年203人が自分の選んだ系列のクラスに分かれ授業を受けました。
授業では、企業の担当者がスライドや仕事で使う道具などを見せながら、「まちの課題解決のために自分たちがなにをしているのか」や仕事の魅力、今後の課題などを説明すると、生徒たちは、熱心にメモを取りながら聞いていました。
最終的に生徒は、昨年度制定された「菊川市こども・若者支援交付金」を参考に10人のグループで資金10万円を活用した菊川市の課題解決につながる「大人を巻き込む企画」を考えていきます。



よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.