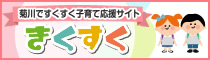ホーム > 市政情報 > ”旬感”まちのニュース > 2024年度 > 令和7年2月まちの話題を紹介します
ここから本文です。
更新日:2025年2月28日
2月28日(金曜日)横地小5年生が日本の伝統楽器「箏」を体験しました
2月28日、横地小学校で日本の伝統楽器「箏」の体験を行いました。地域に住む三浦康子さんや神谷恵子さんを講師に招き、同校5年生児童13人が、日本の伝統楽器「箏」について学びました。
はじめに、三浦さんが、箏について説明。箏は、桐の木でできていて、側面に伝統工芸の蒔絵が描かれていることや弦を弾くときに指につける箏爪の付け方、音の高低を決める役割を果たす柱など、箏について教えてもらいました。つづいて、神谷さんが弾く箏と三浦さんが歌う竹取物語を披露。児童は、教室に響き渡る綺麗な音色に聴き入っていました。
次に、児童が、箏を実際に触り、演奏を体験。児童は、神谷さんや三浦さんに弾く弦を教えてもらいながら一人ずつ「さくら」を最後まで演奏しました。
演奏体験をした男子児童は、「難しそうだと思ったけど、弾いたら楽しかったです。音がすごくきれいだと思いました」と話しました。
5年生の体験につづいて、4年生も同じ内容の体験をしました。



2月24日(月・振)きくがわ健康フェスタ、健康講演会が開催されました
2月24日、文化会館アエルで市制20周年記念事業「きくがわ健康フェスタ」および「菊川市立総合病院健康講演会」が開催され、多くの市内外から多くの方が参加しました。本イベントは、「野菜・お茶×体づくり」をテーマに、さまざまな企画が用意され、来場者は楽しみながら健康について学ぶ機会となりました。
きくがわ健康フェスタでは、「菊川発健康マシマシイベント」と題し、身近な野菜と運動で元気な未来へをテーマにさまざまなイベントが行われました。
野菜・お茶エリアでは、菊川産大玉トマトの無料配布や菊川産芽キャベツの詰め放題が行われ、新鮮な地場産品の販売のほか、六郷小学校の児童がJAなどコラボした菊川茶の販売、お茶の淹れ方教室が行われました。特にトマトの無料配布では、200個用意されたトマトがオープン後わずか30分で終了し、長蛇の列ができるほどの人気ぶりでした。また、芽キャベツの詰め放題ではおよそ20キロが用意されましたが、こちらもおよそ1時間で売り切れるほどの盛況ぶりでした。
健康体験エリアでは、健康体操のコーナーでは、市マスコットキャラクター「きくのん」が登場し、参加者と一緒に「きくがわ体操」を踊って会場を盛り上げました。健康チェックコーナーでは、野菜摂取量を測定するベジチェックや骨密度測定、血管年齢測定などが行われ、自分の健康状態を知る機会となりました。また、菊川市立総合病院の看護師によるなんでも相談コーナーでは、専門家が個別の相談に応じ、健康維持に関するアドバイスを行いました。
大ホールで行われた菊川市立総合病院健康講演会では、同院副院長の阿部雅志さんによる膝関節治療の話が行われた後、イベントの目玉として、特別講師に谷本道哉さんを招き、「1日たった5分!簡単筋トレで健康ボディを手に入れよう」の題目で講演が行われました。およそ500人が参加し、谷本さんから筋肉と健康に関する話や効果的なトレーニング方法などが紹介され、参加者は熱心に耳を傾けていました。また、講演中に参加者と一緒に筋トレを行い、参加者全員で楽しく体を動かしました。



2月20日(木曜日)〜22日(土曜日)代官屋敷梅まつり「竹あかり展」が開催されています
2月20日、国指定重要文化財「黒田家住宅」で「代官屋敷竹あかり展」が開催されました。梅まつりの会場となっている黒田家住宅を竹灯籠の灯りでライトアップすることで、市の新たな観光資源にならないかと、3年ほど前から実行委員会が実施しているもの。市内を中心に竹灯籠の制作や展示の活動を行う「市民活動団体たねあかり」と市観光協会などが協力し、竹灯籠およそ400本を黒田家住宅のシンボルである長屋門の前に並べました。
初日のこの日竹灯籠の温かな光に照らされ、昼間とは違った姿を見せる黒田家住宅の庭園を散策したり、写真を撮ったりして楽しんでいました。
長屋門の前では、小笠北小学校6年生が制作した「卒業記念竹灯籠」が並べられ、かわいらしい図柄が掘られた作品が、来場者を出迎えました。
自分の作品を見に訪れた小笠北小学校6年生の児童たちは、自分の作品がきれいに飾っている様子を家族や友人などと眺めていました。



2月20日(木曜日)「ひらかわサロン」で介護予防講座と寸劇鑑賞が行われました
2月20日、平川コミュニティ防災センターで「ひらかわサロン」が開催されました。同サロンは、地域に住む高齢者の方々に友だちと話をしたり、歌を歌ったりするなど、楽しい時間を過ごしてもらうことを目的に、今年は年4回開催されています。今年度最後となるこの日は、市役所の長寿介護課による出前行政講座「知っておく!から始めるフレイル予防のポイント」と小笠東地区で活動する女性グループ「たいした会」による寸劇「へっこきあねさ」の鑑賞が行われました。
前半の出前行政講座では、介護が必要になる一歩手前で、心身の活力が低下した状態である「フレイル」予防について、「しっかり食べる」「動くことが楽しくなる体づくり」「脳を活性化する」「人と関わり、よく話す」の4つについて、市の職員から話を聞いたり、「きくがわ体操&菊川いきいき体操」を行ったりしました。
後半の寸劇鑑賞では、たいした会のメンバー8人が農夫婦や将軍、お侍の衣装やメイクをして登場。ユーモアあふれる寸劇に会場からは笑いや拍手が起こり、参加者たちは楽しい時間を過ごしました。たいした会代表の二俣みほ子さんは「地域の方が喜んでくれている姿を見ることで元気をもらっています。たいした会を立ち上げておよそ9年が経ち、メンバーも4人から9人に増えました。現在は、月2回、地区センター(くすりん)で活動しています。声を掛けていただき、都合が合えば福祉施設や地区センターなどで寸劇を披露していきたいです」と話しました。



2月16日(日曜日)令和6年度菊川市ペタボード交流会が開催されました
2月16日、小笠体育館で令和6年度菊川市ペタボード交流会が開催されました。老若男女が気軽に楽しめるニュースポーツの一つである「ペタボード」の普及や市民の健康づくりなどを目的に市が主催したもの。家族や友だち、仕事仲間など48人20チームが参加し、仲間とともに楽しく競技に親しみました。
「ペタボード」は静岡県発祥の屋内スポーツで、「ディスク」と呼ばれるプラスチック製の円盤6個を「キュー」と呼ばれるスティックを使って押し出し、青い「ビュット」と呼ばれる的にどれだけ近く寄せられたかで得点を競う競技。冬に行われる「カーリング」に似ており、激しい動きを必要としないため、誰でも簡単にプレーすることができます。
参加者たちは、ルールや競技説明を受けた後、4つのブロックに分かれ競技を行いました。初めてペタボードをやる参加者もいる中、家族や友だちからアドバイスをもらいながら笑顔で競技を行い、ナイスショットが出ると「やった!」「すごい!」と声を出して喜び合い、ペタボードを通しての交流を楽しみました。
年中児1人と小学生2人の子ども、夫の家族5人で参加した中村麻文(あさみ)さんは、「冬だと寒くて外に出づらく、子どもたちが家でゲームばっかりになってしまうので、身体を動かす機会にと参加しました。ルールは簡単だけど、勝つにはテクニックが必要でおもしろいです」と話してくれました。



2月13日(木曜日)JA遠州夢咲いちご委員会がひがしこども園にいちごを贈呈されました
2月13日、遠州地域のいちご生産者で組織するJA遠州夢咲いちご委員会から、ひがしこども園へ夢咲産のいちごが贈呈されました。
旬のいちごを地元の子どもたちに味わってもらおうと同会がJA管内のこども園などで毎年行っている恒例行事。今回は、ひがしこども園に訪問し、「夢咲いちご」およそ240粒を贈呈しました。
贈呈式では、冨口秀樹委員長や役員が、園児たちへ「夢咲いちご」を手渡し、受け取った園児たちは、大きな声で「ありがとうございます」と感謝を伝えました。
冨口秀樹委員長は「地元のおいしいいちごです。おいしく食べてください」と話しました。
同園では、もらったいちごを園内の行事「お楽しみクッキング」で使用したり、おやつの時間に提供したりする予定とのことです。



2月10日(月曜日)児童が集めたお茶殻原料とバイオマスプラスチックでマグネットバーが完成しました
2月10日、小笠北小学校の児童が考案した、市の特産物でもあるお茶の茶殻を原料にしたバイオマスプラスチックを活用したオリジナルのマグネットバーが完成しました。マグネットバーは、同校5、6年生児童が総合的な学習の時間でお茶を飲んだあとの茶殻の有効活用について考え、茶殻を原料にした「バイオマスプラスチック」で作ったもの。NPO法人えくすこらが学校と企業の間に入り、今回、地元企業のマルゼン工業に、加工してもらった長さ25センチ、幅2センチほどのプラスチックの板に子どもたちが磁石を取り付け、オリジナルのマグネットバーを完成させました。
マグネットバーには、「未来につなごう菊川」というキーワードや、湯飲みやペットボトルの絵などが描かれていて、ほのかにお茶の香りがします。全部で500個作られたマグネットバーは、子どもたちがひとつずつ家に持ち帰るほか、地元で開かれているイベントで訪れた人たちに配る予定です。
6年生の男子児童は、「菊川市のいいところをもっと知ってもらうためにがんばりたいです」と話しました。



2月8日(土曜日)第20回菊川市書き初め展表彰式が行われました
2月8日、中央公民館多目的ホールで「第20回菊川市書き初め展」の表彰式が行われました。市民の伝統的な芸術文化に対する意識向上を図り、書写・書道を通じて豊かな人間形成に役立てることを目的に毎年開催しています。今回は、市内在住・在学・在勤の小学3年生以上の人から422点の作品が集まり、その中から13作品が市長賞や議長賞、教育長賞などの特別賞に輝きました。
表彰式では、長谷川寬彦市長が挨拶。自身も長年書道に親しんでいることに触れ、「今回、私も市民の皆さんが今年の漢字1文字に選んでいただいた『翔』を用いて『飛翔』を書いて出展させていただきました。私も皆さんと同じように子どもの頃から書に親しんでいます。旧菊川町時代の書き初め展で入賞して、それがうれしくて励みになって今でも続けています。ぜひ皆さんも書を楽しみながら続けていただき、自分の強みとして磨いてください」と、受賞者を激励しました。また、審査総評では、審査員を務めた中澤皐楊(こうよう)先生が「今年も素晴らしい作品ばかりで審査するのが大変でした。書はその人らしさがでるものです。上手に書こうと思って書くよりも楽しんで書こうと思って書いた作品の方が人に感動を与えられるのではないかと思います。書は一生楽しめるものです。ぜひこれからも書を楽しんでください」と、総評しました。
太く丸みを帯びた筆遣いで「晴れた空」を書きあげ、市長賞を受賞した山本早桜(さお)さんは、「今回の書は、細さや太さの強弱をつけることに気を付けて書きました。来年も賞がもらえるように作品を書き続けたいと思います」と話してくれました。
受賞作品は、2月8日(土曜日)から2月20日(木曜日)まで、中央公民館1階展示ロビーで展示されています。皆さんの力作をぜひご覧ください。
<入賞者一覧>
・市長賞
山本早桜(やまもとさお)小笠北小学校4年
川口結愛(かわぐちゆあ)小笠北小学校6年
植山穂乃花(うえやまほのか)菊川西中学校3年
落合花温(おちあいかのん)静岡中央高等学校3年
・議長賞
鈴木善治郎(すずきぜんじろう)加茂小学校5年
横山紗月(よこやまさつき)内田小学校6年
小山歩莉(こやまあゆり)菊川西中学校1年
・教育長賞
赤堀ゆあ(あかほりゆあ)小笠東小学校3年
小山旺祐(こやまおうすけ)加茂小学校4年
近藤綾音(こんどうあやね)菊川西中学校2年
・文化協会会長賞
牛見紋心(うしみあこ)河城小学校3年
八木彩心(やぎあこ)内田小学校5年
佐野りお(さのりお)菊川西中学校1年



2月6日(木曜日)校歌の話を聞く会~小笠南小学校の校歌に込められた思いを学ぼう、感じ取ろう~
2月6日、小笠南小学校で「校歌の話を聞く会」が開催されました。同校の最上級生になる児童に、愛校心や学校のリーダーとしての意識を高めてもらおうと毎年行われている行事。5年生16人が、校歌の作詞・作曲者である福嶋勲さん(96歳)から校歌が誕生した経緯や歌詞に込めた思いを聞きました。また、今回は、福嶋さんが教員だった時の教え子7人が参加し、福嶋さんの思いを児童と一緒に聞きました。
福嶋さんは、校歌の歌詞を教えるときに、1年生でも歌えるようにやさしく明るい言葉で、当時の学校周辺の風景や子どもたちへ成長の願いを込めて作詞したことを説明しました。また、校歌と同時に誕生した校章には、ウバメガシの葉のように丈夫に育ってほしいという思いが込められたことが話されると、児童はメモを取りながら聞いていました。福嶋さんの教え子だった人たちは、福嶋さんの思いにうなずきながら、懐かしそうに聞いていました。
福嶋さんは、「自分の心を外に出すことが表現で、表現することはとても大切です。校歌も心を込めて表現すると相手に伝わります」と話しました。
最後に、福島さんが指揮をとり児童全員で校歌を歌い、歌詞に込められた思いを改めて感じていました。



2月4日(火曜日)岳洋中学校の生徒が探求学習での成果を発表しました
2月4日、岳洋中学校で同校1・2年生の生徒が、菊川市の魅力や将来の夢を保護者に向け発表しました。自ら課題を見つける力や人前で表現する力の向上が目的。生徒は、総合的な学習の時間に小笠高校の生徒からプレゼンのやり方を教わるなど、探求学習に取り組んできました。1年生は、「菊川市の魅力」、2年生は「将来の夢」について全259人が学習した成果を保護者の前で発表しました。
2年1組では、生徒が4つのグループにわかれ、将来の夢について1人ずつタブレットを使ってプレゼン。「何を基準に仕事を決めたらいいのか」をテーマにした男子生徒は、「自分に合った仕事を見つけるには、自己分析や周りの人に相談すること、仕事を長く続けるには、ストレス発散方法を見つけたり、人とコミュニケーションを積極的にとったりすることが大事だとわかりました」と話すと、グループの生徒はうなずきながら聞いていました。また、プレゼンを聞いたグループの生徒は、感想を付箋に記入して、プレゼンした生徒に渡しました。
1年2組の教室では、4・5人のグループにわかれて自作のモニターを使用し、プレゼン。「深蒸し茶は菊川で誕生しました」をテーマにプレゼンした4人は、深蒸し茶の特徴や身近で使われている食べ物を紹介しました。また、「深蒸し菊川茶がもらったマークはどれでしょう」などのクイズも交えられ、地理的表示(GI)制度に登録されたことを説明しました。
発表を聞いた保護者は、「素晴らしい」「よくまとまっている」などの感想の声が上がり、子どもたちの成長に感動していました。



2月3日(月曜日)「おせっかいの会」から菊川保育園園児に節分豆まき用お菓子が贈られました
2月3日、菊川保育園で市民グループ「元気サロンおせっかいの会」が、園児に節分豆まき用お菓子を贈りました。同グループは、地域の遊休農地で会員が育てた野菜や、家庭菜園の余剰野菜を販売し、購入者が代金の代わりに併設の募金箱へ収めたお金を募金に充当する「野菜福祉募金」を実施しています。今回、社会奉仕活動の一環として、この募金を活用し、同園へ節分豆まき用お菓子が贈られました。
この日は、菊川保育園の園児に節分豆まき用お菓子詰め合わせセット105人分が贈られました。同グループのメンバーから同園園長へ目録が手渡され、同園園長からは同グループへ感謝状が手渡されました。
最後に、サンタやうさぎなどの着ぐるみを着た同グループのメンバーから、園児へ一人ずつお菓子の詰め合わせセットが配られると、園児は「ありがとう」と元気にお礼を言いながら受け取りました。
同グループ会員の村木ユキ子さんは、「今日は、私たちも子どもたちの笑顔を見ることができてうれしく思いました」と話しました。



2月2日(日曜日)黒田家代官屋敷梅まつり&長屋門フェスタ2025が開催されました
2月2日、国指定重要文化財「黒田家代官屋敷」で毎年恒例の梅まつりが始まりました。地域住民で組織する「ひらかわコミュニティ協議会」が中心となり開催しているもので、今年は3月2日までの期間中、普段入ることができない庭園が無料開放され、寒紅梅、白加賀など13種類およそ160本の梅の花を楽しむことができます。
今年は寒さが厳しく、梅の花はまだつぼみの状態でした。訪れた人たちは、春の訪れを心待ちにしながら、つぼみが開花する頃を楽しみにしている様子でした。
初日の2日には、地元の平川地区コミュニティ協議会や平川地区自治会が中心となり、「長屋門フェスタ2025」が開催されました。あいにくの雨模様で、午前中のステージ発表の一部が変更となりましたが、お昼前には雨もやみ、会場となった代官屋敷駐車場には、地域の人による模擬店で飲食物や地場産品の販売が行われたほか、友好交流都市の長野県小谷村のブースで特産品の販売が行われ、大勢の人で賑いました。昨年に続き、「梅干しの種飛ばし大会」も開催されました。黒田家住宅庭園の梅から作った梅干しを食べ、口に残った種を勢いよく飛ばし、その距離を競うもの。この日は小学生の部・一般女性の部・一般男性の部の3部門におよそ20人が参加し、それぞれの部門で白熱した試合が行われました。すっぱい梅を思わず吐き出してしまう子どもや、大きく勢いをつけたのに全然飛ばなかった人など、選手たちの真剣でコミカルな様子に、会場には声援と笑い声が響いていました。
競技終了後、それぞれの部門で1位~3位の記録になった人に賞品が贈られました。最高記録は、一般男性の部に参加した山浦さんは、記録10m11cmで優勝し、商品のお米5キログラムを笑顔で受け取っていました。
小学生の部で、6立方メートル9cmの記録で優勝した6年生の男児は、「初めての挑戦だったけど、意外とうまく種をとばすことができてうれしかったです」と笑顔で話していました。
【黒田家代官屋敷梅まつり】
■開催期間:3月2日(日曜日)まで
■開園時間:午前10時~午後3時※入園無料
■会場:黒田家代官屋敷(下平川862-1)
■問い合わせ先:市観光協会(0537-36-0201))



2月1日(土曜日)市制20周年記念「雪まつり」が開催されました
2月1日、菊川市と長年交流のある長野県小谷村から雪のプレゼントが届き、雪まつりが開催されました。日ごろから雪と触れる機会の少ない子どもたちに雪遊びを楽しんでもらうための恒例行事。多くの地域住民などが参加して、雪との触れ合いや住民同士の交流などを楽しみました。
今年は市制20周年を記念し、なんと例年の2倍の雪が到着しました。小谷村観光連盟や小谷村役場の職員も協力し、10トン大型トラック4台分の雪を使い、雪のすべり台や雪遊びができる広場が設置されました。子どもたちは、普段見ることのない雪に目を輝かせながら、雪山の斜面をソリで滑ったり雪だるまやかまくらなどを作ったりして、楽しみました。また、会場では、「雪中キャベツ」などの小谷村特産品販売が行われたりしました。
長谷川市長は、「菊川はめったに雪が降らないため、子どもたちが雪に触れる機会はほとんどありません。今回は20周年記念ということで、昨年の2倍となるダンプトラック4台分の雪を届けていただきました。小谷村の方々に感謝しています」とお礼の言葉を述べました。



よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.