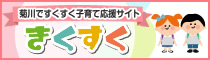ここから本文です。
更新日:2023年10月20日
知っておきたい法律・知識(消費生活)
知っておくと消費生活上役立つ、大切で重要な法律です。
消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)
消費者と事業者の間には情報の質と量、交渉力の大きな差があります。そのため、消費者と事業者が対等に契約できるように生まれた新しいルールが消費者契約法で、平成13年4月1日から施行されました。
- 事業者に不当行為(不当な勧誘行為、不当な契約条項の使用)があった場合、契約の取消や条項の無効を主張できます。
- 消費者と事業者間で結ばれるすべての契約が対象となります。
≪消費者契約法における不当勧誘行為、不当契約条項の例≫
契約を取消にできる不当な勧誘行為
1.不実告知(重要事項について事実と違うことを言われた)
例)「この機械を取り付ければ電話代が安くなる」と勧誘し、実際にはそのような効果のない機械を販売
2.断定的判断の提供(将来どうなるか不確実なことを確実であるかのように断定的に言われた)
例)元本保証のない金融商品を「確実に値上がりする」と説明して販売
3.不利益事実の不告知(有利な点ばかり説明され、都合の悪いことをわざと告げられなかった)
例)眺望・日照を阻害する隣接マンション建設計画を知りながら、「眺望・日照良好」と説明し、当該マンション建設計画の事実を説明しないで販売
4.不退去(事業者が家や職場に居座り帰るよう頼んでも帰らず、長時間にわたり勧誘された)
例)学習教材の訪問販売員に深夜まで自宅に居座られ、「帰って欲しい」と言っても帰らないため、仕方なく契約
5.監禁(帰りたいと言っても事業者が販売所から帰さず、長時間にわたり勧誘された)
例)絵の展示会で長時間にわたり絵の購入を勧められ、「帰りたい」と言っても帰らせてもらえず、仕方なく契約
★不当な勧誘行為に基づく契約の取消権行使期間
誤認に気づいたとき(上記、不当な勧誘行為の1~3)または困惑状態(上記、4~5)を脱したときから1年
もしくは、契約締結から5年
無効にできる不当な契約条項
1.事業者の損害賠償責任を免除する条項
(いかなる理由があっても事業者は一切の損害賠償責任を負わないものとする条項)
2.消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等
(消費者が解約した場合、支払済みの代金を一切返金しないとする条項等)
3.消費者の利益を一方的に害する条項
(賃貸借契約において、借主に過重な原状回復義務を課する条項等)
特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)
特定商取引法は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。正式名称は、「特定商取引に関する法律」。
特定商取引法の対象となる取引類型
特定商取引法の対象となる取引類型は、以下の6つです。
| 訪問販売 | 自宅への訪問販売、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後営業所等に同行させて販売)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)等 | |
| 通信販売 | 新聞、雑誌、インターネット(インターネット・オークションも含む)等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込を受ける販売(「電話勧誘販売」に該当するものを除く。) | |
| 電話勧誘販売 | 電話で勧誘し、申込を受ける販売 | |
| 連鎖販売取引 | 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売 | |
| 特定継続的役務提供 | 長期・継続的な役務(「えきむ」と読む。サービスの意味)の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(現在、エステティックサロン、外国語教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6役務が対象) | |
| 業務提供誘引販売 | 「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引 | |
規制の概要
1.行政規制
事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下の規制を行っています。違反行為は、改善指示、業務停止の行政処分または罰則の対象となります。
| 氏名等の明示の 義務づけ |
勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げることを義務づけ。 | |
| 不当な勧誘行為 の禁止 |
不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止。 | |
| 広告規制 | 1.広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ。 2.虚偽・誇大な広告を禁止。 |
|
| 書面交付義務 | 契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ。 | |
2.民事ルール
消費者と事業者の間のトラブルを防止し、その救済を容易にする等の機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消等を認め、また事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルールを定めています。
| クーリング・オフ | 申込みまたは契約後一定の期間(下表)、消費者は、冷静に再考して、無条件で解約できる。 〈摘要除外〉 1.クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合 2.商品がクーリング・オフ対象ではない場合又は商品が乗用車の場合 3.健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用し、又は一部を消費した場合 (ただし、それでもクーリング・オフができる場合もあります) 4.購入者がセールスマンを呼び寄せて購入した場合 5.購入者が自ら販売業者まで出向いて契約をした場合 6.通信販売で購入した場合 7.現金一括支払いで、かつ代金の総額が3,000円未満の取引の場合 8.個人ではなく「事業者」として契約した場合(法人契約など) |
|
| 意思表示の取消し | 事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み またはその承諾の意思表示をしたときは、消費者は、その意思表示を取り消すことができる。 | |
| 損害賠償等の額の制限 | 消費者が中途解約する際等に、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定。 | |
◎クーリング・オフできる期間
| 取引種類 | クーリング・オフ期間 | 摘要 |
| 訪問販売、 電話勧誘販売 |
クーリング・オフできることを書面で知らされた日から8日間 | 店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3,000円未満の現金取引を除く) |
| 連鎖販売取引 (マルチ商法) |
法定の契約書の受領日または商品の受領日のどちらか遅い日から20日間 | 全ての商品・権利・役務、指定商品制なし、店舗契約も含む |
| 業務提供誘引販売 (内職商法・モニター商法) |
法定の契約書の受領日から20日間 | 仕事を斡旋する対価として備品購入や講習・登録費等の金銭負担をする取引、指定商品制なし、店舗契約も含む |
| 特定継続的役務提供 (エステ・学習塾など) |
法定の契約書の受領日から8日間 | エステ・外国語教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介業(継続したサービスを行う契約)、店舗契約も含む |
通信販売には、クーリング・オフに関する規定はない。
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.