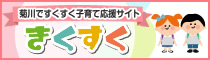ホーム > 市政情報 > ”旬感”まちのニュース > 2025年度 > 令和7年9月まちの話題を紹介します
ここから本文です。
更新日:2025年9月4日
9月29日(月曜日)小笠南小学校児童が稲刈りに挑戦
9月29日、同校5年生の児童25人が、地元の方々やJA遠州夢咲の協力のもと、稲刈りに挑戦しました。6月上旬に自分たちの手で植えて育った稲を、鎌を使いながら一束ずつ丁寧に刈り取りました。あいにくの雨模様でしたが、児童たちは天候に負けることなく、泥だらけになりながら一生懸命作業に取り組み、およそ1時間で全ての稲を刈り終えました。



9月26日(金曜日)横地小学校児童が新作スイーツをプレゼン
同校6年生は総合学習の一環として菊川市をPRする方法を検討する中で、「食を通じて菊川市を盛り上げたい」と考え、地元の人気洋菓子店「patisseriemiel(パティスリーミエル)」と地元の特産品を使った新作スイーツを共同開発することとしました。
9月26日には、児童一人ひとりが考えた新作スイーツを、同店シェフの川中孝美さんにプレゼン。児童たちは、深蒸し菊川茶やイチゴ、ブルーベリー、メロンといった特産品を使ったオリジナルスイーツの特長や思いなどを伝えました。
今回共同開発するスイーツは、11月22日(土曜日)に開催される「横地大好きフェスタ」で販売予定です。どのスイーツが選ばれるかお楽しみに♪



9月25日(木曜日)「灯りの散歩道onハロウィーン」開催に向けて竹灯籠作りワークショップ開催しました
9月25日にシ・イ・ソヒゾ・デ・クリアンサブラジル人学校で、「灯りの散歩道onハロウィーン」の開催に向けて、竹灯籠作りのワークショップが行われました。竹灯籠作りを通して、外国の子どもたちに日本の文化を伝えることが目的。ライトアップなどのイベントを行っている市民団体「たねあかり」塚本隆男さんなどが講師を務め、同校生徒およそ30人が放置竹林を活用して竹灯籠を作りました。
はじめに、同団体の塚本隆男さんが、竹灯籠の作り方を説明。「穴の大きさに合わせてドリルの先端を変えて、穴を開けてください。小さい穴より大きい穴の模様の方が灯りがきれいに浮かび上がります」と話しました。
生徒は、あらかじめ用意されたドリルで穴を開けるための目印を書き加えたイラストから好きな絵柄を選んで、長さおよそ30cm、直径およそ10cmの竹筒に貼り付けました。そして、ずれないように専用の台の上に載せると、電動ドリルを使って穴をあけていきました。初めてドリルを使う生徒もいて、慣れない手つきで慎重にドリルを使っていました。途中、ドリルの直径を変えながら大小の穴を開けて図柄を仕上げていきました。
最後に、塚本さんが、仕上げのガスバーナーで表面を焙ったり、表面を雑巾で丁寧に磨いたりして、図柄の輪郭がキレイに浮かび上がる竹灯籠を完成させました。
講師を務めた塚本隆男さんは、「自分の作った竹灯籠が、灯りの散歩道で展示されることによって、イベントに参加しようと思ってくれたり、会場での楽しみが増えてくれたりしたらうれしい」と話しました。
完成した作品は、10月25日に開催される「灯りの散歩道onハロウィーン」に展示される予定です。



9月25日(木曜日)岳洋中学校で福祉学習を行いました
9月24日・25日、岳洋中学校で福祉学習が行われました。障がいのある人や、高齢者などの立場に立って物事を考えることができる気持ちを育てることを目的に開催。1年生およそ130人が参加し、2日間をとおして福祉とはなにかを学びました。
1日目には、実際に福祉施設で働く職員が講話を実施。職員は、「ふくし」は「ふだんのくらしをしあわせにする」ことであり、高齢者や障害をもつ人だけではなく、全ての人に関わることであると生徒に伝えました。
2日目には、福祉体験を実施。生徒は車椅子体験、アイマスク体験、高齢者体験などを通して、福祉を提供する側と必要とする側の気持ちを体感しました。
高齢者体験で生徒は手足におもりをつけ、視界が狭くぼやけるメガネを装着。その状態で杖を突きながら校内を歩いたり、バスケットボールをゴールに入れたりすることに挑戦。付き添いで歩くグループの仲間の声を頼りに、身体が思うように動かない困難を感じながら歩ていました。
高齢者体験をした生徒は、「とても身体が重く感じ、特に靴を履き替えるのが大変でした。高齢者が大変そうにしているのを見かけたら、積極的に手伝いたいです」と感想を話しました。



9月25日(木曜日)河城小学校で富士山静岡交響楽団による音楽鑑賞会が開催されました
9月25日、河城小学校で富士山静岡交響楽団による音楽鑑賞会が開催されました。本事業は、静岡県文化政策課が実施する「子どもが文化と出会う機会創出事業」の一環として開催されたもので、生のオーケストラの演奏を聴くことにより、音楽活動に興味・関心を持ち、生涯にわたって音楽を愛好する心を育てることを目的としています。この日は全校生徒およそ230人が参加し、全6曲の演奏を満喫しました。
初めに「結婚行進曲」が演奏されたあと、「富士山」のメロディに合わせて、木管楽器、金管楽器、弦楽器、打楽器の順番で楽器紹介が行われました。児童たちは楽器毎に異なる音色に聞き入り、自分たちの気に入った楽器を見つけて楽しそうにしていました。
次に代表児童2人による指揮者体験が行われました。代表児童は、指揮棒を持って指揮台に上がると、緊張しながらも笑顔で、「ハンガリー舞曲第5番」の演奏に合わせて指揮棒を振っていました。曲中のテンポが遅くなったり早くなったりする箇所も見事に指揮し、最後まで指揮し終えると、会場からは大きな拍手が送られました。
また、同校校歌を演奏するという場面もありました。「オーケストラの演奏を伴奏に校歌を歌う」というまたとない機会に、児童たちは演奏に負けないように大きな声で元気に歌っていました。
その他、静岡ゆかりのうたをメドレーにした曲やベートーヴェンの「運命」など、一度は聞いたことがある名曲が演奏されました。
演奏会に参加した児童は「生のオーケストラ演奏を聴くことができて嬉しかったです。こんなに近くで聞くことができて、迫力があってすごかったです」と感想を述べました。
<演奏曲>
1.結婚行進曲/メンデルスゾーン
2.ふじの山~子どものための楽器紹介~★楽器紹介
3.ハンガリー舞曲第5番/ブラームス★指揮者体験
4.河城小学校校歌★演奏に合わせて全校児童で合唱
5.オーケストラで綴る「静岡ゆかりのうた」せいくらべ~羽衣~かわいい魚屋さん~農兵節~赤い靴~汽車ポッポ~みかんの花咲く丘
6.交響曲第5番「運命」第1番/ベートーヴェン



9月25日(木曜日)菊川西中学校でふるさと未来塾が行われました
9月25日、菊川西中学校で同校1年生192人を対象に「ふるさと未来塾」が開催されました。地域の良さや菊川市で働くことについて考えてもらうことが目的。同校や市社会教育課などが連携し、「中学生向けの企業説明会」として実施され、生徒たちは地元で働く意義や魅力について学びました。
市内に事業所を持つ菓子専門店や製造業、病院、社会福祉法人など、14の企業や団体などが講師として参加。生徒は、その中から事前に希望した4つの企業・団体の説明を聞きました。企業の担当者がスライドやそれぞれの職業で使う道具などを用いて自社の魅力を説明。菊川文化会館アエルの講演では、「文化とは心を豊かにしたり、暮らしを豊かにしたり、人と人を繋げます。それを実現するために文化会館があり、バックアップするスタッフがいます」と説明すると、生徒は納得した表情で聞いていました。
小笠北認定こども園への質問コーナーでは、「仕事で辛いことはありますか」と質問が生徒から出され、講師の同園園長は、「子どもたちが成長して大人になった姿を見るととてもうれしいので、大変と思ったことはありません。楽しくてやりがいのある仕事です」と答えました。



9月24日(水曜日)令和7年度シニアクラブ菊川「第39回輪投げ大会」が開催されました
9月24日、小笠体育館で令和7年度シニアクラブ菊川「第39回輪投げ大会」が開催され、シニアクラブ菊川会員およそ108人が熱戦を繰り広げました。
同クラブは毎年会員の体力維持と健康増進、スポーツを通じた親睦交流のために、毎年輪投げ大会を開催。1チーム6人に分かれて、18チームで順位を競い合いました。
開会式では、市長寿介護課の黒田寿通(としみち)課長が「地域の高齢者が集まり楽しく身体を動かすことは、健康寿命を延ばすための大切なことです。これからも、たくさん身体を動かし、いつまでもお元気で、いきいきとした生活を送っていただければと思います」と挨拶。競技説明の後、黒田課長と菊川市社会福祉協議会の酒井幸寛(ゆきひろ)会長の始輪式で競技が始まりました。大会が始まると、参加者はいっせいに輪を投げ、次々と的棒に投げ入れていました。会場には元気な声と笑顔があふれていました。



9月21日(日曜日)第21回菊川市長杯市民グラウンドゴルフ大会が開催されました
9月21日、尾花運動公園で第21回菊川市長杯市民グラウンドゴルフ大会が開催されました。市民の体力維持と健康増進、スポーツを通じた親睦交流のために、菊川グラウンドゴルフ協会が毎年開催しているもの。市民およそ130人がエントリーし、秋晴れの空の下、熱戦を繰り広げました。この日は、8ホール4コースが用意され、個人32ラウンドの合計スコアで順位を競い合いました。
この日の参加者で最高齢は宮原吟生さん(92歳)。大会が始まると、参加者はホールへと繰り出し、夏のような日差しと秋の気配を感じる風が吹く芝生の上で、はつらつとプレーし、次々とナイスショットが飛び出しました。
最高齢の長谷山さんをはじめ、ホールインワンを決める人もいて、会場には元気な声と笑顔があふれていました。



9月19日(金曜日)岳洋中学校で小学生と中学生の合同理科授業が実施されました
9月19日、岳洋中学校で小学生と中学生の合同理科授業が実施されました。小学生と中学生が一緒に授業を行うことを通して、小中学校間の交流や学力の向上を図るろうと初めて実施された取り組み。同中学1年生32人と小笠南小6年20人が、理科の授業2時間を一緒に受け、顕微鏡の使い方を学びました。
1時間目の授業では、同中学校の理科教諭が、ゾウリムシやミドリムシなどの4種類の微生物を顕微鏡で見る方法を説明すると、児童は緊張している様子で聞いていました。
説明後、中学生がビーカーに入った微生物入りの水をスポイトでスライドガラスに垂らしプレパラートを作成。次に、小学生がプレパラートを顕微鏡にセットし、接眼レンズから微生物を観察しました。中学生は小学生に、「微生物が見やすくなるように反射鏡を動かしてみて」「開口絞りを絞るとピントがあうよ」などのアドバイスをすると、微生物がはっきり見えた小学生は、「気持ち悪い」「たくさんいる」などいいながら、夢中になってレンズから見ていました。
授業を受けた小学生は、「はじめは緊張したけど、中学生が優しく教えてくれたから分かりやすかった」と、中学生は「小学生と一緒の授業は楽しい」と話しました。
2時間目には、「物質を顕微鏡で見ると~粒子概念の導入~」をテーマに小学生と中学生が協力して考察結果をまとめる授業を行いました。



9月18日(木曜日)「東海トレセンU-13東海地域対抗戦」出場選手が教育長を表敬訪問しました
9月18日、「東海トレセンU-13東海地域対抗戦」に出場する選手が、教育長を表敬訪問しました。同大会は、9月21日に愛知県で開催され、静岡県トレセンメンバーとしてソーニョFC掛川に所属する池谷琉希選手が選ばれました。
トレセンとは、日本サッカー協会が推進するナショナルトレーニングセンター制度(トレセン制度)の略称で、選抜された優秀なユース年代(小学生から高校生)の選手たちに、日本サッカー全体の発展を目指したトレーニングや指導の機会を提供することを目的としたシステムです。
池谷選手は、「得意なドリブルで自分の個性をだしていきたい」と、教育長に向け意気込みを話しました。
松本教育長は、「トレセンにはうまい選手がいて緊張するかと思いますが、臆することなく自身の強みをアピールし、積極的にチャレンジしてください。力を発揮できるように応援しています」と激励しました。



9月15日(月曜日)おでかけラジラin菊川
9月15日のK-MIXモーニングラジラは、プラザきくるから出張公開生放送が行われました。パーソナリティの「ズミさん」こと、高橋正純さんの軽快なトークを楽しもうと、会場には市内外からおよそ350人のファンが駆け付け、多くの立ち見客が出るほどになりました。市内に製造工場を持つたこ満や協賛企業の皆様が出演したほか、長谷川市長も出演し、菊川市の魅力をたっぷり紹介できた時間となりました。放送後は菊川茶のティーバッグなどが当たるじゃんけん大会が開かれ、来場者はズミさんとの交流を満喫しました。






9月13日(土曜日)第20回菊川市障害者スポーツ友愛大会が開催されました
9月13日、市民総合体育館で第20回菊川市障害者スポーツ友愛大会が開催されました。障がいがある人がスポーツを通じて、体力の増進増強や、残存能力の向上を図り、明瞭快活な性格と強調精神を養うことで自立更生の実を挙げ、明るい希望と勇気をもってたくましく生きる能力を育むことを目的に開催される恒例イベント。
市内に住むさまざまな障がいをもつ人たちやボランティアなどおよそ70人が参加し、和やかな雰囲気の中、大会のテーマである「友愛」の精神のもと、輪投げ、スカットボール、パン食い競争の3競技を通じて交流を深めました。
輪投げとスカットボールでは、狙った箇所に輪やボールが入ると、互いに歓びを分かち合ったり、競技のコツなどを教え合ったりしていました。聴覚障害を持つ人たちへは、手話でルールを説明したりと、工夫をして競技を楽しんでいました。
パン食い競争で用意されたパンは、社会福祉法人草笛の会が運営するB型就労継続支援事業「草笛共同作業所」で作られたもの。この日はアンパンとクリームパンの2種類が用意されました。参加者たちは、笛の合図とともにパンをめがけて走りだし、吊るされたパンを一生懸命取っていました。



9月10日(水曜日)三遠ネオフェニックスの元バスケットボール選手とバスケ交流会
9月10日、小笠南小学校で元プロバスケットボール選手とのバスケ交流会が行われました。プロバスケットボールクラブ「三遠ネオフェニックス」がバスケットの普及活動の目的に開催。同チームの元選手2人から、同校6年生21人がバスケの楽しさや自分の得意なことを見つけて伸ばす大切さなどを学びました。
講師を務めたのは、鹿毛誠一郎(かげせいいちろう)さんと岡田慎吾(おかだしんご)さん。はじめに2人は、自己紹介とあわせバスケを始めた経緯やプロ選手になるために必要なことなどを児童に話しました。児童は身長が2メートル以上ある鹿毛さんと180センチ以上ある岡田さんに興味津々。鹿毛さんは「身長が伸びる人はたくさん寝て、たくさん食べる人が多いです。皆さんも丈夫な体を作るため夜更かしせずよく寝てよく食べてください」と長身になる秘訣を児童に教えました。また、岡田さんはプロ選手に必要なことを伝授。「プロは誰にも負けない強みを持っている人がなれます。みなさんも好きなことを継続することで得意なことを作ってみてください。またバスケの実力だけでなく、英語や国語力、計算など今皆さんが勉強していることがとても必要になります」と自身の経験をまじえて話すと、児童は真剣な表情で聞いていました。
講義が終わると、早速ボールを持って実践。鹿毛さんがシュートのコツを話すと、児童は次々とゴールに向かってボールを投げシュート練習をしていました。最後は、鹿毛さんと岡田さんを相手にミニゲームに挑戦。元プロ選手のディフェンスを破り見事にゴールを決めると、児童たちから大歓声が沸き上がりました。
交流会を終えた男子児童は、「苦手だったシュートが、コツを意識して投げたら少しできるようになりました。体を丈夫にするため普段の夜更かしを減らしていきたいです」と話してくれました。



9月9日(火曜日)内田小学校で男女共同参画職業講話が開催されました
9月9日、内田小学校で男女共同参画の意識啓発を図る職業講話が開催されました。幼少期から男女共同参画の意識啓発を行うため市が主催し、市内の小学校で毎年実施しているもの。この日は、菊川市警察署に勤める小野清花さんと菊川市立総合病院に勤める看護師の山本宗吉さん、落合峻賀良さんを講師に招き、同校6年生児童26人が、性別にとらわれなく、将来の職業選択を考えることの大切さを学びました。
講師の2人から、従事している仕事や現在の職業に就こうとしたきっかけなどについて説明が行われると、普段では聞けない内容に児童は真剣な表情で聞き入りました。
小野さんは、「人の役に立ったり自分も成長できたりする仕事に就きたくて警察官を目指しました。警察官は、働く場所が数年で異動するので、つねに新しいことを覚えなければいけないことは大変ですが、経験が豊富になり今後の仕事にも生きています。とてもやりがいのある仕事です」と語りました。
また、菊川市立総合病院に勤める看護師の山本宗吉さんは、「小学校の時に、骨折をして半年入院した経験があります。その時に、優しく接してくれた看護師に憧れましたが、当時は、男性は看護師になれないと思っていました。新聞で、男性も看護師になれると知ってから、看護師を目指すことができました。看護師は、大変なことも多いですが、患者さんから『ありがとう』と言われたときは、とてもやりがいを感じます」と話しました。
最後に児童は、3つのグループに分かれ、各講師に質問をしました。看護師の落合さんは、「看護師になるには6年生から何年かかる?」「仕事で大変なことは?」などの児童からの質問に丁寧に答えていました。
講話を聞いた児童は、男性だから、女性だからと決めつけるのではなく、性別にとらわれない社会の大切さを実感していました。
9月末までに本講座は、他牧之原小学校や市内4校でも開催される予定です。



9月7日(日曜日)田んぼアート菊川収穫祭が開催されました
9月7日、水田に巨大な絵を浮かび上がらせる「田んぼアート」の収穫祭が、下内田の稲荷部地区の田んぼアート菊川会場で行われました。地元住民のほか、市内外から親子連れなどおよそ200人が参加。黄金色の稲穂を、家族や仲間とともに丁寧に刈り取っていきました。
今年の絵柄は「富士山と駿河湾」。全国初となる田んぼアートでのトリックアートに挑戦しました。今年は3種類の古代米を使用し、絵柄を表現しています。
参加者は、主催者の田んぼアート菊川実行委員会メンバーから、稲を刈る際の注意点の説明を受けた後、3種類の古代米が植えられたおよそ1,600平方メートルの田んぼの稲を手で収穫していきました。参加者は鎌を手に田んぼの中に入っていくと、実行委員会のメンバーに教えてもらいながら、稲を1束ずつ刈っていきました。刈り終わった稲は種類ごとに束ねて稲架けしていきました。
田んぼアート菊川実行委員会の池田正さんは、「金曜日の大雨の影響が心配でしたが、会場の田んぼには被害が出ず、今日を迎えることができて良かったです。鑑賞期間中は多くの人に来場いただき、大変嬉しく思っています」と話しました。



9月4日(木曜日)小笠北小学校で冬野菜の種まきを行いました
9月4日、小笠北小学校2年生児童およそ50人がレタスの種まきを行いました。種まきから収穫までの野菜作りを体験し、野菜への関心を高めることを目的とした「食育体験授業」の一環として実施。児童は市内の農業法人である株式会社ソイルパッションの社員から野菜が自分たちの手元にくるまでの行程を学びました。
はじめに、同社の代表・深川知久さんがスライドを使い、野菜が収穫できるまでにいくつもの工程があることや、虫や鳥から野菜を守る方法などを説明。説明を聞いた児童は、早速深川さんらの指導の下種まきに挑戦しました。班ごとで協力しながら、苗を育てる容器に土を敷き、器具を使って深さ5mmの穴を開け、丁寧に種をまいて、最後に覆土を振りまきました。種まきを終えた児童の佐野紗帆さんは、「家が農家を営んでいて、おじいちゃんやお父さんが作業をしている姿を見たことがあるが、自分で種を蒔いたのは初めてです。楽しかったので、またおうちでもやってみたいです」と感想を話しました。
深川さんは、「スーパーで並んでいる野菜は、小さい種からできていて、いくつもの工程を経て自分たちの手元まで来ているということを知ってもらい、食への感謝の気持ちを感じてくれたらうれしいです」と話しました。
今後、児童はブロッコリーやキャベツの苗も育て、草取りや虫取り作業など手入れをしながら、それぞれの野菜の収穫時期に合わせ収穫する予定です。



9月2日(火曜日)中央公民館でシニア健康体操教室が開催されました
市内で60歳以上を対象とした連続5回教室「シニア健康体操教室」が開催されています。スポーツでいつまでも健康な状態を維持してもらうことや、教室を通じて人との交流を深めてもらうことを目的に、社会教育課が実施。高齢者でも気軽に行うことができるヨガやトランポリンなどバラエティに富んだ体操を、全5回の教室で行います。第1回目の今回は、市民12人の参加者が、ヨガ・ノルディックウォーク講師の山田祥子(さちこ)さんから、2本のポールを使ってウォーキングする「ノルディックウォーク」を教わりました。
はじめに、山田さんがノルディックウォークの発祥の地がスウェーデンであることや、ポールを使ってウォーキングすることの効果を説明。「ポールを使ってウォーキングすると、消費カロリーが20%アップし、さらに4点歩行になることで膝や腰にかかる負荷が3割程度軽減します」と話すと、参加者は驚いた様子で聞いていました。
つづいて、参加者はポールの使用方法について説明を受けた後、屋内でノルディックウォークを練習。はじめてポールを使用したウォーキングに挑戦する参加者は、はじめぎこちない様子で歩いていましたが、徐々に慣れてくると胸を張り良い姿勢が保てるようになってきました。最後には、屋外に出て今日の学びを実践。景色を見ながら楽しくウォーキングを楽しんでいました。参加者は、「ポールの使い方や体への負担も少ないことを知ったので、ウォーキングを継続できるように頑張りたいです」と話しました。



よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.