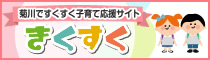ホーム > 市政情報 > ”旬感”まちのニュース > 2025年度 > 令和7年6月まちの話題を紹介します
ここから本文です。
更新日:2025年7月1日
6月26日(木曜日)堀之内小学校で「交通安全リーダーと語る会」が開催されました
6月26日、堀之内小学校で「交通安全リーダーと語る会」が開催されました。交通安全リーダーを担う同校の6年生児童が、通学路の危険な場所について、危険な理由と対策を考えることで、安全を確保して登下校できるようにすることが目的です。
児童たちは、地区ごとに分かれ、各自が持つタブレットで地図や写真を使いながら、自分たちが思う通学路での危険場所を洗い出し、状況を確認しました。その後、同席した菊川警察署職員や交通安全指導員、交通指導隊、保護者たちにアドバイスをもらいながら、安全に登下校できるよう、“自分たちでできること”や“地域の皆さんにお願いしたいこと”を話し合いました。
話し合い後、警察署職員と交通安全指導員からは、「通学路は毎日歩いていると慣れてしまい、危険な箇所に気付けなくなってしまいます。今日皆さんが改めて考えた危険な箇所などに注意して、下級生のお手本となるようにしてください」と講評しました。
参加した児童は、「私が普段使う通学路は細い道が多いです。下級生には、一列になって車道にはみ出さないようすることを伝えたいです。かなりスピードを出している車が多いので、ゆっくり走ってほしいです」と話しました。



6月23日(月曜日)菊川市消防署で花火教室が開催されました
6月23日、菊川市消防署で花火教室が開催されました。園児に、花火の正しい取り扱い方法や火の危険性を学んでもらうことが目的の恒例行事。地域で防火啓発活動をしている市消防職員から、双葉こども園年長の園児と保護者の30組が、火の安全な使い方を学びました。
はじめに、親子は、消防署の2階大会議室でDVDを鑑賞し、火遊びの危険性について学びました。次に、消防署職員が、安全な花火の遊び方や服に火がついた時の対処法を説明。園児は、実際に火が付いたことを想定して、火を消す動作を行いました。その後、親子は、消防署の外で花火に火を付けて安全な遊び方を学びながら、花火を楽しみました。
同教室は、6月から7月にかけて、市内幼稚園・保育園・認定こども園の全13カ所で行われています。



6月20日(金曜日)ひがしこども園の園児が消防署を見学しました
6月20日、ひがしこども園年長児30人が消防署を見学しました。施設見学を通じて消防署の仕事や火災予防の大切さを学び、消防署への理解や防火意識の向上を図ることを目的に消防署が開催している恒例行事。消防署内や消防車・救急車の見学や、訓練の見学、防火服を着る体験をしました。
施設見学では、トレーニング室や仮眠室、食堂などの部屋を一つひとつ回り、消防士がどのようなときに使用するのかを園児に説明。仮眠室では、「消防士は24時間働いているので、仮眠室では布団がおいてあり休憩ができます」と職員が説明すると、園児は驚いている様子でした。消防車や救急車の見学では、署員が車両ごとに役割があることや、積載されたさまざまな装備品について解説。園児は、普段なかなか入ることのできない救急車の中にも入り、設置してある機材をじっくり見学していました。最後に、消防士のレスキュー隊員が防火衣の早着替えを披露。園児が30秒を数えている間に、素早く着替えたレスキュー隊員を見ると「かっこいい!」「はやい!」と歓声を上げていました。レスキュー隊員は、「少しでも早く助けに行けるように、防火衣を早く着る練習をしています」と説明していました。
見学を終えた園児は、「消防士になりたい!」と元気に話してくれました。
同施設見学は、他市内幼稚園・保育園・認定こども園に向けても今後実施する予定です。



6月17日(火曜日)菊川の野菜って美味しい!地産地消の給食を提供しました
市では、学校給食への地産地消を推進する取組として、市内の地場産品を給食に使用する「ふるさと給食週間」を行っています。6月17日には、ベルファーム株式会社が栽培したアスパラガスを使ったソテーやトマト使ったミネストローネなどの献立が、市内全小中学校で提供されました。当日は、堀之内小学校に同社職員が訪れ、循環型農業の取組を伝えながら、一緒においしい給食を楽しみました。



6月14日(土曜日)令和7年度菊川市体力測定会&健康チェックの日が開催されました
6月14日、菊川市民総合体育館で、「令和7年度菊川市体力測定会&健康チェックの日」が開催されました。体力・運動能力の現状を把握するための調査として、市内在住、在勤、在学者を対象に市社会教育課が主催する体力測定会と、市健康づくり課で行う健康チェックが同時に開催されたもの。自身の体力年齢や現在の健康状態を確かめました。
体力測定会では、握力測定や上体起こし、長座体前屈など全9項目のブースが設置され、参加者は、それぞれの年齢に合わせた6項目のブースにて体力測定を行いました。測定後は、自身の記録をシートに記入していきました。
健康チェックでは、体組成測定(インボディ)や骨密度測定、野菜摂取量測定(ベジチェック)などの5つのブースとスタッフによる健康相談が設置され、参加者は、スタッフから測定結果の説明を聞きながら、改めて自身の身体・健康と向き合いました。

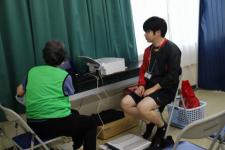

6月12日(木曜日)小笠東小学校で「福祉のお仕事魅力発見セミナー」を行いました
6月12日、小笠東小学校で社会福祉協議会が主催する講話「福祉のお仕事にも魅力がいっぱい!」が行われました。同校では、総合的な学習の時間に「福祉」をテーマに探求学習に取り組んでいます。学習の過程で、児童が、福祉に関わる人に関心を持ったことから実施。同校4年生28人が、社会福祉法人大東福祉会の土井孝久(たかひさ)さんから、福祉の仕事の魅力を教えてもらいました。
はじめに、土井さんは、同会がどのような会社か説明。次に、介護施設で働く人は、大きく分けて「介護職」「看護職」「リハビリ職」「生活相談員」「ケアマネジャー」などさまざまな職種があり、それぞれの職種で役割があることを話しました。土井さんが、介護をする中で大切にしていることは、「介護を必要とする人の気持ちを大事にし、自分でできることは自分でやってもらうように支援します」「笑顔でコミュニケーションすることを大事にしています」と話すと、児童は、納得した様子で聞いていました。
最後に、質問の時間が設けられると、児童から「スーパーで歩行器などを使っているお年寄りを見かけたらどうしたらいいですか」などと質問されると、土井さんは、「突然手助けをするのではなくて、『困っていませんか?』と声かけをするのがいいと思います」など、1つひとつの質問に丁寧に答えていました。



6月12日(木曜日)浜松いわた信用金庫創立75周年記念車両贈呈式
6月12日、きくる広場で浜松いわた信用金庫創立75周年記念車両贈呈式が開催されました。同庫が創立75周年を記念して、本店や支店のある県西部の7つの市町にスズキ・ジムニーが合わせて30台が贈呈。そのうち菊川市には2台が贈られることになり、贈呈式では、髙桝裕久理事長より長谷川寬彦市長へレプリカキーが手渡されました。同庫のシンボルマークと同色である青色と黄色の車両です。
髙桝理事長は、「皆様のおかげで75周年を迎えることができ、感謝の気持ちを込めて車両を贈呈いたします。車両は地元の名車であるジムニーを選びました。悪路の走破性も高いため、平時だけでなく有事の移動手段として役立ていただきたいです」と話しました。
長谷川市長は、「山間部でも大変目立つ良い色だと思います。この色を安全安心の目印として平時はもちろん有事の際にも活用させていただきます」とお礼を述べ、感謝状を贈呈しました。



6月12日(木曜日)加茂小学校で租税教室が開催されました
6月12日、加茂小学校で租税教室が開催され、同校6年生88人が税の仕組みと大切さを学びました。次世代を担う子どもたちに、税のことを知ってもらうことを目的に、掛川税務署や掛川税務署管内の地方税関係機関、教育関係機関などで構成される「掛川税務署管内租税教育推進協議会」が主催し毎年開催しているもの。今年度は、市内の小学校2校で租税教室を行います。
市税務課職員が講師となり、黒板にイラストをはりながらクイズやパンフレットなどで税金の使い道や納税の方法について説明しました。その後、税金がなくなった世界を仮定したビデオを視聴。児童は、税金でまかなわれているから救急車で運ばれても料金が掛からないことや、自分たちが過ごしている学校も税金で建てられていることなどを学びました。また、1億円分の紙幣のレプリカが入ったケース(およそ10キログラム)を実際に持ち上げる体験をすると、「すごく重たい」など驚きの声を上げていました。
最後に講師は、「皆さんの身近の人が働いて税金を払ってくれています。学校の机や教科書など大切に使って、勉強を楽しんでください」と児童へ伝えました。
講座を最後まで聞いた澤入羽琥(わく)さんは、「税金を払わないと大変な世界になってしまうことや税金の仕組みがわかりました」と話してくれました。



6月5日(水曜日)EU欧州連合農業・食料担当委員とビジネス使節団が菊川市に来訪しました
本の農林水産大臣に相当する、EU欧州連合のクリストフ・ハンセン欧州委員会農業・食料担当委員とビジネス使節団が菊川市に来訪しました。
長谷川市長との面会後、市内で茶の有機栽培を行っている岩沢園の茶園を訪れ、GI登録されている「菊川深蒸し茶」と世界農業遺産である「茶草場農法」を視察しました。また、同園で飼育しているポニーによる循環型農業についても説明を受け、菊川市の魅力を体感していただきました。
菊川深蒸し茶を試飲したハンセン氏からは「柔らかい苦みがあり、リフレッシュできる」と講評いただき、「伝統を重んじ、次世代に繋げていくための持続可能な農業を続けてほしい」と大変ありがたいお言葉をいただきました。
この機会を大切に、今後の菊川茶の海外展開に繋げてまいります。



6月5日(木曜日)自分を励ます魔法の言葉「ペップトーク」を学生に
6月5日、常葉大学附属菊川中学校・高校の体育館で創立記念日教育講演会が開催されました。6月8日が同校の53回目となる創立記念日であることから開催され、同校生徒およそ1150人(中学生150人、高校生1000人)が参加。日本初の「アスレチックトレーナー」であり、一般財団法人日本ペップトーク普及協会代表理事の岩﨑由純氏が講師を務め、生徒達に“やる気を引き出す魔法の言葉“「PEPTALK(ペップトーク)」を広めました。
岩﨑氏はまず、「オリンピックに行くこと」という夢を持った中学時代から実際にアスレチックトレーナーとしてオリンピックに行くまでの経緯を紹介。「夢をずっと信じ続けていれば、姿を変えて現れることがある。そのためには、好きなことも嫌いなことも頑張り続けなければならない。その頑張りを支えてくれるのが『言葉の力』である」ことを伝えました。そして、やる気や潜在能力を引き出すコミュニケーション技法である「ペップトーク」について、「自分を励ます言葉がけ」であり、「できることを前向きな表現で言葉にする」ことだと紹介。岩﨑氏は、ペップトークをするためには、捉え方をポジティブに変換する必要があると「疲れた→本気で頑張った証拠」「怒られた→大切なことを学んだ」など例を用いながら生徒に分かりやすく説明していました。最後に、岩﨑氏は生徒たちに「できる、できる、必ずできる!」と三々七拍子を送り「今の自分を受け入れてください、全ての努力は必ず力になります」とメッセージを伝え会場を後にしました。
今回の講演を経て、岩﨑氏は、「学生さんたちだからこそ夢の話をしました。今回の講演を聞いた皆さんが、ペップトークを活用してなりたい自分になるための努力を今から初めてくれたらうれしいです」と話しました。



6月5日(木曜日)小笠地区の茶生産者が地域の子どもたちにお茶を寄贈されました
6月5日、小笠地域の茶生産者で組織するJA遠州夢咲小笠茶業委員会から、小笠地域の幼保こども園4園と小中学校4校へ飲み茶が贈呈されました。
深蒸し茶を地元の子どもたちに毎日飲んでもらい、お茶を身近に感じてほしいという思いから同会が毎年行っている恒例行事。同会の役員が各園や学校を訪問し、小笠地区内の製茶工場で作られたティーバッグ全およそ8Kgを贈呈しました。認定こども園ひがしこども園では、片山裕司委員長、鈴木直之副委員長、宮城克司役員が訪れ、年長児32人へ直接、およそ8Kgのお茶を手渡しました。お茶を受け取った園児たちは、大きな声で「ありがとうございます」と感謝を伝えました。
片山委員長は園児に「このお茶を飲んで、みんな毎朝元気よく登園してください」と話しました。お茶を受け取った河島芽依ちゃん(6歳)は、「いつもおうちで家族みんなでお茶を飲んでいます。温かいお茶が好きです」と話しくれました。
同園では、もらったお茶を昼食の時に提供するほか、水分補給用としても活用するとのことです。



6月3日(火曜日)愛育保育園で人権教室が開催されました
6月3日、愛育保育園で人権教室が開催されました。この教室は、幼少期から命の大切さや友達、周りの人と仲良くすることの大切さ、そして日常のあいさつの大切さを学ぶことを目的に毎年開催されています。同園の年長児20人が参加し、掛川人権擁護委員協議会菊川地区研究会の委員8人から人権について学びました。
はじめに、委員が「人権とは何か」を園児に分かりやすく説明。その後、委員による「どっちだゲーム」が行われ、「唐揚げとサラダどっちが好き?」「カラスとアヒルどっちが好き?」など委員から質問された園児は、「唐揚げー!」「アヒル―!」など大きな声で答えました。委員が、「どちらが好きでもよくて、みんな違っていいのよ」と伝えると、園児は納得した様子で聞いていました。
続いて、人形劇「ケンカのあとのごめんなさい」では、ケンカをしたあとは「ごめんなさい」の言葉を伝えあうことで、そのあともお互いに笑顔で気持ちよく過ごすことができることを伝えました。
劇を見た園児からは、「ごめんなさいって言えてえらかった」「ケンカしたら、ごめんなさいって言う」など感想を話しました。最後に同会から、参加した園児に、人権イメージキャラクターのマスコットや折り紙などの人権啓発品が贈られました。



6月2日(月曜日)人権擁護委員の日にあわせて、啓発活動が行われました
6月2日、掛川人権擁護委員協議会菊川地区研究会の人権擁護委員が、しずてつストア菊川店で街頭広報を行いました。6月1日が「人権擁護委員の日」であることから、人権擁護委員の存在と役割を知ってもらうことを目的に毎年実施しています。同会の委員4人と市職員1人が、買い物客らに「人権擁護委員です。よろしくお願いします」と声を掛けながら人権擁護委員の活動と相談窓口を紹介するパンフレットと啓発物品を配布しました。
同会で10年間人権擁護委員を務めた白松和子委員は、「幼稚園や小学校では、人権教室を通して人権の大切さを伝えられますが、一般の方には伝える機会が少ないため啓発活動をしています。悩みがある人に一人でも多く、心が軽くなる手助けができればと思います」と話しました。
6月5日には、田子重小笠店でも同様の啓発活動を行う予定です。



6月1日(日曜日)令和7年度菊川市水防訓練を実施しました
6月1日、菊川下内田地区河川防災ステーションで水防訓練が行われました。同訓練は、出水期に備え水防作業技術の向上や水防体制の強化などを図ることが目的。菊川市水防団や市危機管理課職員のほか、地域住民で構成される自主防災会、防災指導員などおよそ300人が訓練に取り組みました。昨年度に引き続き、陸上自衛隊6人が訓練に参加し、より強度な土のう作成技術を指導しました。
訓練では、陸上自衛隊が、堤防の決壊を未然に防ぐ「土のうこしらえ工」「積み土のう工」の作り方について説明。袋を裏返しにすることで縫い目を内側にして土を入れると劣化を防げることや、土のうを積むときには叩いて空気を抜くことで水の侵入を防げることなど、作り方だけでなく、より強度の高い土のう作りのポイントが説明されました。
その他、消防署員の指導のもと、万が一の際に自分や要救助者の安全を確保するための「本結び」、「もやい結び」、「巻き結び」の方法を習得する「ロープ結索訓練」が実施されました。
訓練後、国土交通省浜松河川事務所の行方敏剛(なめかたとしたか)副所長は、「本日の訓練では、具体的な土のう作りを行い、水防活動を自分事として訓練することができたと思います。土のう作りは水防工法の最初のステップです。この地域の安全・安心を守るため、本日の学びを今後の迅速な水防活動に生かしてほしいです」と講評しました。



6月1日(日曜日)菊川河口周辺の海岸清掃を実施しました
6月1日、掛川市国安の一級河川菊川の河口で実施。昭和51年より実施している恒例行事で、掛川市・菊川市の市民や企業、市職員などが多くの方が参加しました。河口や海岸に落ちているごみを拾い、1時間ほどでコンテナいっぱいのごみが集まりました。これからも、豊かな自然に恵まれた、美しい河川や海岸線を皆さんでつくっていきましょう!



よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.