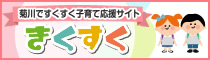ここから本文です。
更新日:2024年11月30日
11月30日(土曜日)ぶらり文化財散歩~虚空蔵山と秋葉灯籠をめぐる~が開催されました
11月30日、「ぶらり文化財散歩~虚空蔵山と秋葉灯籠をめぐる~」が開催されました。地域に残る身近な文化財のことを知ってもらおうと、市埋蔵文化財センターが開催している恒例行事。今年は、市内外から38人が参加。小笠南地区に残る文化財や史跡を巡りながら、ウォーキングを楽しみました。
小笠南地区コミュニティセンターを出発した一行は、センターの北側の丘陵上に建つ「南山浅草観音堂」とその裏手にある古墳時代の横穴墓跡を見学しました。
次に参加者は観音堂から地域の農業を支える前岡池に沿って北へ歩き「虚空蔵山」に移動しました。虚空蔵山に隣接する山西郷土資料館では、保管されている大正から昭和にかけての日用品などの資料を見学しました。
その後、一行は山道を歩き、高橋地区のお寺「宝積寺」の参道入り口に残されている秋葉街道の常夜燈を見学しました。常夜燈は瓦屋根の小屋のような形をしていて、中に秋葉神社のお札が祀られています。市埋蔵文化財センターの丸杉俊一郎指導主事が「このような常夜灯は、ここから東にある正林寺というお寺から東西方向に数多く残されていて、このあたりから掛川市の横須賀へ向かっていたのだと考えられます。常夜灯をたどると当時の主要な道がどのように続いていたかがわかります」と説明すると、参加者は感心した様子で聞いていました。
その後も「熊野神社の梛の木」や「坊之谷の常夜灯」「河東のお地蔵さん」を見学しました。坊之谷の常夜灯は山の斜面を掘って作った珍しい常夜灯です。丸杉指導主事は「木製の常夜灯やよくある石の常夜灯は管理が大変であることや、この地域の山が比較的柔らかい地質で掘りやすかったこともあって、当時の人はこのような常夜灯を造ったのではないかと推察しています」と説明すると、参加者は興味深そうに説明を聞き、写真を撮っていました。
出発から3時間ほどでスタート地点の小笠南地区コミュニティセンターへ帰ってきた参加者は、最後に完歩の記念品として、埋蔵文化財センターオリジナルのメモ帳を受け取りました。市内から参加した女性は「菊川に住んでいても知らないところを案内してもらえるので、毎年楽しみにしています。虚空蔵山は名前は聞いたことはありましたが、今回初めて行きました。また参加したいです」と感想を話しました。



11月24日(日曜日)加茂地区文化祭が開催されました
11月24日、加茂小学校体育館と加茂地区センターで開催。地域サロンの活動報告の展示や文化サークルの手芸、折り紙、写真などの作品が数多く展示され、訪れた人は、多彩な作品をじっくりと眺めていました。ステージ発表では、地域で活動を行う音楽サークルやフラダンスグループなどによる演奏や踊りの発表があり、日ごろの成果を思いっきり発表すると、訪れた観客から盛大な拍手が送られました。



11月17日(日曜日)フェスタ河城2024が開催されました
11月17日、河城地区センターで開催。潮海寺祇園囃子のステージや、マグロの解体ショー、棚田倶楽部の五平餅の販売など河城地区ならではの企画が行われました。屋内では、地区住民による作品展示や、アートペイントなども行われ、子どもから大人まで楽しんでいました。



11月17日(日曜日)フェスタ西方が開催されました
11月17日、西方地区センターで開催。今年は、ご当地アイドル“さっき―”が司会を務め、菊川西中学校の演奏や、子ども漫才「信天」など楽しいステージを盛り上げました。屋内でも、ペーパークラフトやアートフラワー展などの企画が用意され、会場はたくさんの人で賑わっていました。



11月17日(日曜日)横地地区センターまつりが開催されました
11月17日、横地地区センターで開催。毎年恒例「ラムネ早飲み大会」はもちろん、「10m超ロングパット」や「ボクシングゲーム」など参加型ゲームが盛りだくさん。景品ゲットのために、多くの子ども達が参加の列を作っていました。その他、地元住民によるステージや、地元ならではの販売・展示なども行われ、訪れた人は楽しいひと時を過ごしていました。



11月17日(日曜日)第15回みねだ会館祭りが開催されました
11月17日、みねだ会館で「第15回みねだ会館まつり」が開催されました。屋外では、地元自治会によるゲームコーナーやわたがし、スイーツ販売などのブースが並んだほか、浜岡吹奏楽団の演奏やクラシックバレエなどのステージ発表が会場を盛り上げました。大きな家康くんふわふわも設置され、来場者は楽しいひと時を過ごしていました。
屋内では、地区住民による刺繍絵やアートフラワー、ボタニカルキャンドルなどの作品展示が行われ、訪れた人はじっくり見て眺めていました。



11月17日(日曜日)第16回くすりん祭りが開催されました
11月17日、小笠東地区「くすりん」で開催。体育館では常葉大菊川中高等学校吹奏楽部による演奏のほか、地元団体や個人による舞踊、歌唱などのステージが披露されました。屋外では、巨大なきくのんフワフワや野菜や花が販売される軽トラ市が開かれたり、ヨーヨー釣りや消防車の展示コーナーが設置されたりと、訪れた地元住民が子どもから大人まで楽しんでいました。



11月10日(日曜日)菊川産業祭2024が開催されました
11月10日、文化会館アエルで市制20周年記念「菊川産業祭2024」が開催されました。およそ2万8000人が訪れ、さまざまなブースの出展や活気あるステージで賑わいました。
出展ブースでは、109の企業や団体が出展。市内や周辺市町の地場産品の販売や企業による体験コーナーブースが立ち並び、訪れた人はグルメやまちの技術などを楽しんでいました。また市内、周辺市町だけでなく市と友好都市協定を結ぶ長野県小谷村と、災害協定を結んでいる岩手県滝沢市、交流のある岐阜県瑞穂市なども出展し、それぞれのまちの特産品が販売され、普段なかなか買うことのできない県外の特産品を前に、たくさんの人で賑わっていました。
ステージではおよそ15組の団体が出演。茶娘の衣装を着た市内小学2年生のミニ茶娘による「ちゃこちゃん音頭」の披露や、市内高校生による吹奏楽の演奏やダンスの披露など迫力あるステージが会場を盛り上げました。また、スペシャルゲストとしてM-1グランプリ2023ファイナリスト菊川市出身お笑い芸人の「くらげ」が登場し、漫才を披露。市出身ならではの「地元ネタ」も混ぜながら、会場を爆笑の渦に巻き込みました。
また、今年は市制20周年を記念し、小ホールロビーで市制施行から1年ごとにでき事を振り返る写真が掲載されたパネル「20周年の歩みパネル展示」が行われたほか、イベントの最後には「菊川市制20周年餅まき」が行われました。餅まきには、長谷川市長や10代目菊川茶娘、初代菊川茶公士の他、くらげも参加し、ステージ下に集まった大勢の観客にもちを投げると、観客は楽しそうに「こっちに投げて!!」と声を上げながら盛り上がっていました。
その他、ミニ四駆を走らせたり作ったりできる体験コーナーや、巨大な鉄道模型の展示コーナーなど大人から子どもまで楽しめる体験コーナーが設けられ、会場は多くの親子連れで賑わいました。






11月9日(土曜日)六郷ふれあいフェスタが開催されました
11月9日、六郷小学校と六郷地区センターで「六郷ふれあいフェスタ」が開催されました。六郷まちづくり協議会が毎年開催する六郷ふれあいフェスタに合わせて、今年は地域住民や常葉大学附属菊川高等学校の生徒から学んだり、発表したりする交流プログラムが六郷小学校で初めて開催され、体育館のステージでは、4年生による合唱や6年生のソーラン節、双葉保育園の園児による双葉太鼓が披露され、多くの人が会場に訪れました。
ふれあいフェスタでは、地元住民による写真コンクールやアートフラワー、生け花などの作品が数多く展示され、また、7年かけて作成した駿府城天守閣の木像模型の展示もあり、訪れた人はじっくり見て眺めていました。
そのほかにも、健康づくり推進委員の健康チェックコーナーや農産物の販売や綿菓子など、大人から子どもまで楽しめるプログラムが盛りだくさんで、会場は元気な笑い声や沢山の笑顔でいっぱいとなりました。



11月9日(土曜日)わくわく消防体験プログラムが開催されました
11月9日、「わくわく消防体験プログラム」が市消防本部で開催されました。防火意識の啓発や、消防の仕事について理解してもらうことが目的の恒例行事。幼児から小学生までの親子159人が参加し、さまざまな体験を楽しみました。
参加者は、ロープを渡る訓練や煙を充満させた部屋からの避難、消防車の乗車体験や放水訓練、人形を使った心肺蘇生体験といった5つの体験コーナーをスタンプラリー形式で巡り、消防士の訓練を体験しました。
すべてのコーナーを体験した児童には、菊川市制20周年のロゴマークと消防車や救急車などのイラストがあしらわれた特性の缶バッジが配布され、もらった子どもは大喜びで持ち帰っていました。



11月9日(土曜日)ザ・ロイヤルエクスプレス歓迎イベント
11月9日、JR菊川駅構内でザ・ロイヤエクスプレス歓迎イベントが行われました。このイベントは、11月~12月に静岡県内で運行する東急の豪華観光列車「ザ・ロイヤルエクスプレス」が、JR菊川駅に停車することから、同列車の乗客に旅の思い出を作ってもらうとともに、菊川市のPRを行うことを目的に市とJR菊川駅が企画したもの。事前に応募のあった地域の親子連れ10組20人が列車の到着に合わせてホームで旗を振り、歓迎しました。また、鉄道ファンや、居合わせた駅利用者などが美しいブルーの車体の写真を撮るなどして、賑わいを見せました。
そのほかにも、ホームの一角には、乗客を対象とした市のふるさと納税返礼品の特設コーナーが設けられ、茶娘が深蒸し菊川茶の試飲サービスを行ったり、アローマメロンの試食が行われたりしました。
このイベントは12月14日まで毎週土曜日(全6回)に開催されます。



11月8日(金曜日)小笠北小学校で動物愛護教室が開催されました
11月8日、小笠北小学校で動物愛護教室が行われました。県動物保護協会小笠支部が主催し、動物との触れ合いを通じて動物愛護意識を育成すること、犬に関する正しい知識の普及を図ることを目的に毎年開催しているもの。同校4年生児童73人が参加し、犬の飼い方や正しい触れ合い方を学びました。
児童は、県動物保護協会の職員から動物に関する法律や病気の話、犬の特徴などについて説明を受けた後、聴診器を使って犬と人間の心音を聞き比べ、同じ命を持つ生き物だということを学びました。
次に、協会職員が犬との正しい触れ合い方を児童の前で実演。「飼い主さんに触っていいか聞くこと」や「急に触ろうとすると犬がビックリするので、触るときは上からではなく、下から手をグーにして出す」ことなどの注意点を説明しました。その後、児童は動物愛護ボランティアが飼っている「ジャーマンシェパード」や「トイプードル」などの大小8頭の犬と触れ合い、学習した犬との接し方を実践しました。はじめのうちは少し怖がっている児童もいましたが、次第に打ち解けていき、撫でたり抱きかかえたりと優しく触れ合っていました。
参加した児童は、「初めて犬と触れ合いました。貴重な経験ができてうれしいです!」「犬と触れ合う時の正しいマナーを知ったので、教えてもらった方法で犬の接し方を意識してみたい」と感想を話しました。
最後に、市動物愛護会松本実(みのる)会長から動物愛護に関する本が贈呈され、代表児童が受け取りました。



11月8日(金曜日)市制20周年を祝う特別な学校給食が提供されました
11月8日、市制20周年をお祝いする特別メニューが市内の小中学校などの学校給食で提供されました。このメニューは、学校給食への地産地消を推進する事業の1つとして、市内の地場産品を給食に数多く使用する「ふるさと給食週間」の最終日に実施したもの。市制20周年を記念した献立として、菊川産トマトが入ったメンチカツや菊川産ブロッコリーを使用したサラダ、デザートに市のマスコットキャラクター「きくのん」がデザインされた菊川茶を使ったプリンなどが、学校給食としておよそ4,130食を提供されました。
小笠南小学校では、長谷川市長と松本教育長がそれぞれ訪問し、小学6年生と1年生の教室で児童と一緒においしい給食を楽しみました。長谷川市長が訪問した6年生の教室では、「おいしそう!」と目を輝かせ、いただきますの挨拶をすると、勢いよく食べ始めました。
また、給食中に栄養教諭から献立や地産地消について説明があり、菊川産の農産物をふんだんに使用したメニューであることを知った児童は、地域の郷土料理をより味わって食べていました。
給食を食べた同校6年生の新井ウェンディさんは、「トマトが大好きです。メンチカツはお肉とのバランスが良くおいしかったです!お茶プリンはまた食べたいです!」と笑顔で感想を話しました。



11月7日(木曜日)みなみこども園で防火教室が開催されました
11月7日、みなみこども園で防火教室が開催されました。園児に、火の危険性を学んでもらい、防火意識を高めることが目的の恒例行事。同園の園児66人が参加し、火の安全な使い方を学びました。
はじめに、園児は火遊びの危険性を学ぶDVDを鑑賞。子どもだけで火を使わないことや火事になったらすぐに逃げることを学びました。次に消防署職員や女性消防団員から、服に火がついた際の対処法「止まる」「倒れる」「転がる」を教えてもらうと、園児は床の上で上手に転がって火を消す動きをしました。また、火事が起きたときに避難する訓練では、白い布を煙に見立て、煙よりも下をはって逃げる訓練を行いました。園児は、口元をハンカチなどで覆いながら素早く布の下を通り抜けました。最後に、消防車両の見学が行われ、園児は間近で見る消防車に興味津々な様子でした。
同教室は、10月から12月にかけて、市内幼稚園・保育園・認定こども園で行われます。



11月5日(火曜日)~8日(金曜日)菊川市花の会による「菊花展」が開催中です
11月8日まで、庁舎東館「プラザきくる」屋外階段横と市役所本庁1階ロビーで、「菊花展」を開催しています。市花の会が、市の花である「菊」を栽培し展示することで、市民に「菊」の美しさや華やかさを感じてもらい、魅力を知ってもらうことを目的に開催。今年は、出展者37人から寄せられたおよそ234鉢の菊の花が展示されました。
プラザきくる前では、色鮮やかなかわいらしい「スプレー菊」や「ドーム菊」など様々な種類の小菊の鉢が並べられ、通りがかった人をひきつけていました。また、本庁舎1階ロビーでは、上品な佇まいの大輪の花や、菊を盆栽のように育てた「盆栽菊」が展示され、プラザきくる前とは違った古風な雰囲気に包まれていました。
希望者には、花の販売も行っています。今が見ごろの菊の花をぜひお楽しみください。



11月2日(土曜日)~3日(日曜日・祝)市制20周年記念「第20回菊川市文化祭」が開催されました
11月2、3日の2日間、文化会館アエルで市制20周年記念「第20回菊川市文化祭」が開催されました。市文化協会を中心に組織された実行委員会が企画・運営する総合芸術文化イベント。文化活動を行う個人や団体が日頃の成果を会場で発表しました。
2日間の芸能ステージ部門に21団体が出演。吹奏楽やバンド、ウクレレなどの演奏のほか、モダンバレエでは、音楽に合わせて華麗な演技が披露されると、会場からは盛大な拍手が送られました。
展示アート部門では、絵画や書、写真、生け花、アートフラワーなど12団体の385点の作品が展示されたほか、作品を作れる体験コーナーもあり、会場は作品をじっくりと眺める人や団体の人に作品の見どころを訪ねるなど、文化の交流が広がっていました。



11月3日(日曜日・祝日)「みんなのアソビバ」と「小さな収穫祭」が開催されました
11月3日、プラザきくるときくる広場で『みんなのアソビバ』と『小さな収穫祭』が開催され、親子連れなどおよそ300人が訪れました。小笠高校と常葉大学附属菊川高校の市内2つの高校のコラボ企画で、高校生たちが自分たちの得意な分野を活かし、誰もが楽しめるイベントを開催。地域の人との交流を通して、まちの賑わいづくりにも貢献します。
企画から運営までを若年世代が中心となって実施しています。生徒の成長・活躍の場として展開することで、多くの市民に高校生が発信する菊川の魅力や元気を体験してもらいます。
常葉大学附属菊川高校美術・デザイン科の生徒が企画した『みんなのアソビバ』では、きくる広場に人工芝のマットを敷き詰め、誰でもが自由に遊べる空間に大変身させました。高校生たちが企画し、イラストなども自分で手掛けたアートをモチーフにした6つの「アソビ」が体験できるブースが設けられ、子どもたちは、「ぬりえ」や「パズル」、「魚釣りゲーム」などのコーナーを回り、ブース担当の高校生たちと触れ合いながら、体験を楽しんでいました。
小笠高校の生徒が企画した『小さな収穫祭』では、同校生徒が育てているお茶の試飲や市内の竹林で採れたタケノコの試食、大抽選会などが行われました。また、同校の生徒と市内福祉施設草笛の会が共同企画した新作パン『ユニバーサルパン』の販売も行われました。誰にでも食べやすいパンを作りたいという想いから、中身に白あんと生地には菊川茶が練り込まれています。担当した生徒は、「誰にでも安心して食べられるので、たくさんの人に味わってほしいです」と話しました。



11月3日(日曜日・祝日)第16回みなみやま会館まつり~みんなの文化展~
11月3日、小笠南地区コミュニティセンターで「菊川市制20周年記念第16回みなみやま会館まつり~みんなの文化展~」が開催されました。今年で16回目の開催となる恒例行事で、会場には、地域住民の絵画や書、手芸や工作や、高橋地内の子どもの居場所づくりとして開設しているこどもの文化センターや認定こども園みなみこども園、小笠南小学校の全生徒の作品など300点以上の作品が集まりました。
今回もステージ発表が盛大に行われ、8団体が演奏や踊りを披露しました。オープニングでは岳洋中学校吹奏楽部による演奏が披露され、J-POPやアニメのテーマ曲、懐かしい曲などみんなで楽しめる楽曲を元気よく演奏し、会場は大いに盛り上がりました。また、琳明書道教室による書道パフォーマンスや宮坂流友銭会の傘おどりなどが披露され、会場からは温かい拍手が送られました。
屋内では、子ども向けのお菓子すくいが行われ、親子連れで長蛇の列ができました。お菓子がたくさん入った桶からスコップでお菓子をすくい上げるもので、子どもたちは真剣な表情で挑戦。お目当てのお菓子が取れると、大喜びしていました。
また、昼休みにはじゃんけん大会が行われ、大人から子どもまで楽しく参加していました。



11月2日(土曜日)内田地区ふれあいフェスタ2024が開催されました
11月2日、内田地区センターで「内田地区ふれあいフェスタ2024」が開催されました。内田地区コミュニティ協議会が、地域住民の交流を深め、地域を元気にしようと開催しているもの。地区センターと隣接する内田小学校で、同校児童が日ごろの学習の成果を発表する「内田小学校わくわく発表会」が合同で開催され、多くの人が会場に訪れました。ふれあいフェスタでは、地元住民の書やちりめん細工などの作品が数多く展示され、また「菊川歴史くらぶ」による郷土の偉人展示もあり、訪れた人はじっくり見て眺めていました。
そのほかにも、健康づくり推進委員の健康チェックコーナーやミニロボット操作体験会、農産物の販売や綿菓子や甘酒などの無料で配られるなど、大人から子どもまで楽しめるプログラムが盛りだくさんで、会場は元気な笑い声や沢山の笑顔でいっぱいとなりました。



11月2日(土曜日)令和6年度市民交流プログラム「院内体験ツアー」が開催されました
11月2日、菊川市立総合病院で令和6年度市民交流プログラム「院内体験ツアー」が開催されました。子どもたちに菊川市立総合病院のことや病院の仕事について興味をもってもらおうと同院が企画し開催したもの。市内の小学4年生から中学2年生の親子20組が、普段はなかなか見ることのできない病院内の見学をしたり、医療職が行っている業務の一部を模擬体験したりしました。
はじめに、参加した子どもたちは、医療用の服(スクラブ)に着替えた後4つのグループに分かれ、5つの体験を行いました。「手術室ってどんなとこ?」の体験では、参加者が実際の手術室の中に入って見学をしました。手術室の自動ドアは壁の窪みに足を入れて開けることや手洗いをするときも足でスイッチを押して水や洗剤を出すことを教えてもらうと、児童は驚いた様子でした。手術室内では、本物の医療器具「腹腔鏡用鉗子」を使って異物に見立てたビーズをつまんで動かす体験や、医療用の針と糸で人体に見立てたスポンジを縫合する体験を行いました。
ロビーでは車いす体験が行われ、児童が保護者を車いすに乗せて、障害物を避けながら安全に素早く目的地にたどり着けるか体験しました。狭い場所や段差があるところに差し掛かると、児童は慎重に車いすを押して、通行していました。
臨床工学科では、人体構造のいろいろな形状に関する詳細な画像を見ることができる医療用画像処理ソフトウエアを使って、術前のシミュレーションを体験。VRゴーグルを装着した参加者は、3Dの映像に「すごい!」と言いながら驚いていました。
臨床検査科では、実際に電極を手や足につける体験を行う心電図検査や試験管の中で薬と血液を混ぜて血液型を調べる体験を行う血液型検査が行われました。
看護師の仕事に興味があると話す中学2年生の参加者は、「病院にどんなお仕事があるのかや看護師の仕事がよくわかりました」と話してくれました。



11月1日(金曜日)小笠南小学校5年生児童が自分たちで収穫したお米を販売しました
11月1日、小笠南地区コミュニティセンター駐車場で、小笠南小学校5年生児童22人が自分たちで収穫したお米を販売しました。
総合学習の一環として、米作りの大変さや食の大切さを学ぶことを目的に行っているもの。児童が地元農家の協力を得ながら5月に田植えを、9月に地元農家が機械で稲刈りを行い収穫したお米を「22のあいじょう」と命名し、チラシを作るなどして購入を呼びかけていました。
会場となった小笠南地区コミュニティセンターには、販売開始前から地域住民らが集まり、列を作っていました。販売開始時間になると児童は、「いらっしゃいませ~」と言いながら、用意されたレジに、並んでいるお客さんを手際よく案内していました。また、看板係の児童が、お客さんを最後尾に案内をしたり、同センター前の歩道で「いらっしゃいませ~」と元気よくお客さんを呼び込んだりしていました。さらに、1袋購入につき1回のくじ引きができて、米1合や児童が製作したステッカーが当たるサービスも盛り込まれていました。1袋2合入り150円のお米は飛ぶように売れ、20分ほどで用意した198袋が完売しました。
買いに来た人は「子どもたちが作ったお米を、毎年買いに来ています。栗ご飯にしたり、炊き立ての白米をそのまま食べたりなど色々な形で、お米の味を楽しみたいです」と話しました。
お米を売り終えた鷲山明莉(あかり)さんは、「販売準備や販売開始にお客さんがたくさん来てくれて案内するのが大変だったけど、とても楽しかったです。いい経験ができました」と話しました。



よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.