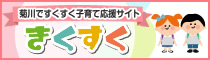ここから本文です。
更新日:2023年12月12日
12月19日(火曜日)横地小学校でお正月用寄せ植え体験が行われました
12月19日、横地小学校でお正月用寄せ植え体験が行われました。花や緑に親しみ、育てる機会を通じて優しさや美しさを感じる気持ちを育てることを目的に毎年実施。市緑化推進協議会、放課後子ども教室のボランティア4人を講師に招き、同校1年生19人が直径30センチほどの鉢にお正月用の寄せ植えを体験しました。
はじめに、同会の内藤すみ江さんが、寄せ植えの作り方の手順を1つずつ説明。鉢の底に赤玉土を入れた後、内藤さんが「ポットから出す前の花を、自分の好きな並べ方で置いてみてください」と説明すると、児童は、ピンクなどのパンジー3本や紫色のビオラ1本、庭木のコニファー1本の配置を考えながら置いていました。つづいて、鉢に土を入れて、花をポットから取り出し、自分で決めた配置に植えていきました。最後に「扇」や「タイ」、市内で刈り取った「稲穂」などの飾りをつけて、思い思いの正月寄せ植えを完成させました。
寄せ植えが完成した堀川穂羽(ほのは)さんは、「はじめて寄せ植えをして楽しかったです。家に持ち帰って玄関に飾りたいです」と話しました。



12月15日(金曜日)おせっかいの会から菊川中央こども園園児にクリスマスプレゼントが贈られました
12月15日、菊川中央こども園で市民グループ「元気サロンおせっかいの会」が、園児にクリスマスプレゼントを贈りました。同グループは、地域の遊休農地で会員が育てた野菜や、家庭菜園の余剰野菜を販売し、購入者が代金の代わりに併設の募金箱へ収めたお金を募金に充当する「野菜福祉募金」を実施しています。今回、社会奉仕活動の一環として、この募金を活用し、市内の認定こども園や幼稚園へクリスマスプレゼントが贈られました。
この日は、菊川中央こども園の園児にクリスマス用のお菓子の詰め合わせセット160人分が贈られました。同グループのメンバーから園児代表4人へ手渡されると、園児たちはうれしそうに受け取りました。また、園児代表から同グループへ感謝状が手渡されました。
最後に、サンタやうさぎなどの着ぐるみを着た同グループのメンバーから、園児へ一人ずつお菓子の詰め合わせセットが配られると、園児は「ありがとう」と元気にお礼を言いながら受け取りました。
同グループの落合岐良代表は、「今日は、私たちも子どもたちの笑顔を見ることができて元気をもらえました。子どもたちの笑顔は地域の宝です」と話しました。



12月14日(木曜日)菊川茶海外輸出戦略に関する協定が締結されました
12月14日、市と佐川急便株式会社が全国初となる菊川茶海外輸出戦略に関する協定を締結しました。地場産品の海外向け販路拡大による地域の活性化を目的とした同社と菊川茶の海外需要拡大を模索していた市双方の目的が合致したことから実現したもの。
締結式では、長谷川寬彦市長と同社の森裕一郎執行役員兼中京支店長兼東海支店長が協定書に署名しました。長谷川市長が「佐川急便様との協定締結を機に菊川茶を世界190カ国以上の国や地域に向けて販路拡大に取り組めることは本当にありがたいです。深蒸し菊川茶が世界に愛されるように期待します」と話すと、森執行役員は「歴史ある菊川茶を世界に届けるお手伝いができることを嬉しく思います。菊川市様と協働し、佐川急便がこれまで培ってきた輸出に関するノウハウを使って、認知向上と販路拡大に貢献したいです」と今後の展望を話しました。
同社の強力なご支援のもと、菊川茶の安全かつスムーズな海外輸出を実現していくとともに、菊川茶が世界に求められるお茶となるよう期待します。



12月6日(水曜日)消防本部職員が手話を体験しました
12月6日、市消防本部で手話の体験講座が行われました。緊急時や災害時に手話を言語とする聴覚障害者から的確に情報を得ることを目的に開催。同本部職員21人が、出前行政講座を活用して、ろうあ者から聞こえない人の生活や手話を学びました。
はじめに、市福祉課職員が平成29年4月に制定された「菊川市手話言語に関する条例」について説明。職員が、「手話は言語のひとつであり、手話を必要とする人が、手話を使って、いつでもどこでも安心して生活できるようにしていきましょう」と話すと、同本部職員は真剣な表情で聞いていました。
次に、市身体障害者福祉会ろうあ部の藤原基時(もととき)部長から、耳の聞こえない人の生活では、どんな場面で困るのかを説明。つづいて、同ろうあ部の池中義一(よしかず)さんから、耳の聞こえない人たちが災害時に避難所でどのように行動するのかを説明し、「耳が聞こえません」などと書かれたとバンダナを首に巻くようにしていることなどを紹介しました。
最後に、同本部職員が緊急時によく使う手話の練習が行われ、同本部職員は講師のお手本を参考にしながら「大丈夫ですか?」と尋ねるときは、相手の顔をのぞき込みながら両手で握りこぶしを作ることなどを学んでいました。
市消防本部の水島浩人主査は、「耳の不自由な人に安心感をもってもらえるよう、今後も手話講習を続けていきたいと思います」と、女性消防救助隊員は、「今回、学んだ手話を今後の救助活動に活かしていきたいと思います」と話していました。
同ろうあ部の藤原部長は、「救助隊の人たちが手話を覚えて何か起きたときのために手助けしてもらえればとても心強いです」と話していました。



12月4日(火曜日)男女共同参画啓発事業「絵本読み聞かせ」が行われました
12月4日、小笠北幼稚園で男女共同参画啓発事業「絵本読み聞かせ」が行われました。市では、幼少期における男女共同参画の意識啓発を図るため、市内の保育園、幼稚園、認定こども園を訪問し、男女共同参画に関する絵本の読み聞かせを行っています。幼いころから「男だから」「女だから」という偏見を持たないことが大切であるため、子どもたちに絵本を通して「自分らしくあることの大切さ」を楽しく学んでもらいます。例年地域支援課の職員が訪問していましたが、今年度は市民団体「やなぎ文庫」に読み聞かせを依頼。絵本やペープサートを使いながら子どもたちに伝えます。
同団体の三浦さんは、男女共同参画の視点を含む絵本「わたし」、「よーいどん」、「なんのくるまにのるのかな」、「ピンクはおとこのこのいろ」の4冊の読み聞かせを行いました。「ピンクはおとこのこのいろ」では、どの色も男の子だから、女の子だからこの色ではなく、人それぞれ「好きな色」があってもいいことを伝えました。最後に、ペープサートを使った、むかし話「ネズミの嫁入り」を楽しみました。
三浦さんは、「強いときや弱いときの心があっていいです。自分のことを大事にしてください」と園児に伝えました。
この事業は、8月から1月まで市内の幼保こども園13園と牧之原保育園で実施されています。



12月3日(日曜日)パニガーレMTG(ミーティング)開催されました
12月3日、菊川文化会館アエル駐車場で、「パニガーレMTG」が開催されました。イタリアのオートバイメーカー、ドゥカティのスポーツバイク「パニガーレ」のオーナーによる交流会で、今年で5回目。菊川市での開催は昨年に続き2回目です。パニガーレ単独のミーティングイベントは世界中を見てもここだけであり、北海道から九州まで全国から毎回およそ400台が参集し、来場者はお互いの愛車を見せ合いカスタムやペイントのこだわりを語り合いながら交流を深めました。
また、今回イベントの中で「1カ所に集まるパニガーレの台数」のギネス世界記録に挑戦。長谷川寬彦市長が証人として立ち合い、集合写真の撮影と、台数のカウントが行われました。集計の結果は132台で、この結果をギネスワールドレコーズ公式認定へ提出する予定です。その他ドゥカティの部品を供給している市内企業の(株)ミクニや国内正規代理店ドゥカティジャパン、ドゥカティ浜松、などの多くのメーカーや飲食店も出店し会場を盛り上げました。



12月2日(土曜日)小笠児童館小学生チャレンジGO!「クリスマス会&オーナメント作り」
12月2日、小笠児童館でクリスマス会が開催されました。同館が小学生を対象に、新しいことにチャレンジできる行事を企画し毎月開催している「小学生チャレンジGO」の一環で行われたもの。市内小学生18人が参加し、光るオーナメント作りやゲームをして一足早いクリスマスを楽しみました。
光るオーナメント作りでは、プラスチック製の丸く透明なオーナメントにシールやマジックを使ってデコレーションをしました。児童達は、クリスマスツリーやベルのシールを貼ったり、白いペンで雪を描いたりと、クリスマスならではのオーナメントを思い思いに装飾。でき上がると、オーナメントのスイッチを入れて光らせ、児童館の職員に「みて!できた!」と嬉しそうに報告していました。
オーナメント作りが終わると、児童は職員によるクリスマスをテーマにしたパネルシアターを見たり、伝言ゲームをしたりと職員が企画したクリスマス会を楽しみました。また、会の最後には職員からのクリスマスプレゼントが用意されました。プレゼントは全面に模造紙が貼られた棚に隠されていて、児童は一人ずつパンチをして探し出すと「あった!」とにっこりの笑顔でプレゼントの袋の中を覗いていました。



12月2日(土曜日)菊川市人権講演会が開催されました
12月2日、菊川文化会館アエル大ホールにて菊川市人権講演会が開催されました。菊川市、掛川市、御前崎市で構成される掛川人権啓発活動地域ネットワーク協議会の事業として3年に1度開催されるもの。今年は、御前崎市出身の陸上競技選手である飯塚翔太さんによる講演が行われ、来場したおよそ150人が人権についての理解を深めました。
講演会では、はじめに掛川人権擁護委員協議会菊川地区研究会の人権擁護委員による活動状況発表が行われ、日頃から市内の小学校や幼保園での人権教室を開催していることや、人権週間に合わせ人権啓発物品を配り啓発活動に取り組んでいることなどを発表しました。また、小学校の人権教室で実際に披露している人権の学びを深める寸劇「ふたつの心」を実演。アドリブを交えた実演に、会場からは時折笑い声が響いていました。
続いて、飯塚さんによる講演「世界と走る」が行われました。飯塚さんは、スポーツを通してさまざまな国籍の人と分け隔てない交流をしてきた経験を紹介。全く異なる文化に触れ驚いた事や難しさなどを話し、その中でもスポーツは言語、文化関係なくつながることのできる「共通語」であることを伝えました。また、アスリートとして人間力を高めるために、心掛けてきたことや習慣としていることを話し、講演が終わると会場からは大きな拍手が送られました。



よくある質問と回答
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.