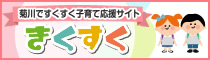ここから本文です。
更新日:2023年11月17日
11月22日(水曜日)横地小全校児童が保護者の前で「能楽」を発表しました
11月22日、横地小学校で全校児童が「能楽」を披露しました。学習発表会である、「横地大好き発表会」の一環で発表。保護者およそ60人の前で、宝生流能楽師シテ方、佐野登さんの舞いと共に全校児童100人が謡う、能楽「鶴亀」謡が披露されました。
児童達は、佐野さんを講師に迎え7月から能楽の練習を開始。佐野さんは、新しいことに挑戦する姿勢や生き方などを児童に熱心に伝えてきました。特に、「よく見て、聞いて、真似る」ことを教えてきて、本番では、その成果が発揮され全員がしっかり謡を覚え、体育館に響き渡る大きな声で謡いきりました。
演舞後、佐野先生は「よく見て、聞いて、真似ることはスポーツや勉強、人付き合いなど学ぶ基本です。また、自分の思いをしっかりと口に出して伝えることも大切です。今回の経験が、何かの目標に向かう場面で活かされることを願っています」と児童達へ想いを伝え、代表児童は、「最初からは上手にできないけれど、諦めずに練習を重ねればできるようになることを学びました。今回の経験は自分の自信になりました」と佐野先生へ感謝を伝えました。
演舞を見た4年生の保護者は、「一流のプロから学べることは大変貴重な機会です。多くのことを学んでほしいです」と話しました。



11月20日(月曜日)加茂小学校で火災防災訓練と防災教室が行われました
11月20日、加茂小学校で火災防災訓練と防災教室が行われました。空気が乾燥し火災が発生しやすくなる時期となることから、学校生活の中で火災が起きた場合の避難の方法を身に付けるために実施。全体での避難方法の確認と学年ごとの防災教室を行いました。
はじめに、家庭科室で火災が発生し、校舎全体に燃え広がる恐れがある状態を想定し、避難訓練が行われました。火災を知らせるベルが鳴り響くと、児童は静かに廊下に整列し、非常階段から屋外に落ち着いて避難しました。その後、学年ごとに分かれ、防災教室を実施。消防署員や県西部地域局職員から災害時に備え何を準備するのか、災害時にはどのような行動をとれば良いのかを考え、火災から命を守るための方法を学びました。
1年生は消防車両の見学を行い、消防隊員からポンプ車の役割や装備の説明を受けました。2年生は火災発生時を想定した煙避難体験。口をマスクやハンカチで覆い、背を低くして壁を手で確認しながら壁沿いを進み、脱出する方法を実践しました。3年生は、避難袋のすべり台の使い方の説明を受けました。4年生は、防災クイズで「身を守る方法」を学び、5年生は、水消火器を使った消火訓練を実施。消防署員から初期消火の大切さや、火事を見つけたときは大きな声で周りの大人に知らせること、子どもだけで消火器を扱わないことや消火する前に自分の逃げ道を決めておくなどの注意事項が説明された後、実際に水消火器の使い方を体験しました。児童は、はじめから火の中心を狙って消火するのではなく、少しずつ近づきながら手前から消火することなどの注意点を守りながら、実践しました。6年生は、災害時判断ゲームを体験しました。同局職員から、学校や家で大きな地震が起きた時に、外に逃げるか建物の中で避難するかなどゲーム方式で、「自分だったらどうするのか」をグループの友だちと話し合い、楽しみながら防災のことを学びました。



11月14日(火曜日)小笠東小学校で動物愛護教室が開催されました
11月14日、加茂小学校で動物愛護教室が行われました。県動物保護協会小笠支部が主催し、動物との触れ合いを通じて動物愛護意識を育成すること、犬に関する正しい知識の普及を図ることを目的に毎年開催しているもの。同校4年生児童85人が参加し、犬の飼い方や正しい触れ合い方を学びました。
児童は、県動物保護協会の職員から動物に関する法律や病気の話、犬の特徴などについて説明を受けた後、聴診器を使って犬と人間の心音を聞き比べ、同じ命を持つ生き物だということを学びました。
次に、協会職員が犬との正しい触れ合い方を児童の前で実演。「飼い主さんに触っていいか聞くこと」や「触るときは上からではなく、下から手をグーにして出す」ことなどの注意点を説明しました。その後、児童は動物愛護ボランティアが飼っている「ジャーマンシェパード」や「トイプードル」などの大小8頭の犬と触れ合い、学習した犬との接し方を実践しました。はじめのうちは少し怖がっている児童もいましたが、次第に打ち解けていき、撫でたり抱きかかえたりと優しく触れ合っていました。
参加した児童は、「犬と触れ合う時のマナーがよく分かりました。次に動物と触れ合う機会があった時は、正しいマナーで触れ合ってみたいです」と感想を話しました。
最後に、市動物愛護会松本実(みのる)会長から動物愛護に関する本が贈呈され、代表児童が受け取りました。



11月13日(月曜日)プロラグビーチーム静岡ブルーレヴズが菊川市長を表敬訪問「きくがわ応援大使」にも就任
11月13日、プロラグビークラブ「静岡ブルーレヴズ株式会社」の山谷拓志代表取締役社長が、シーズン開幕に向けて長谷川寬彦市長を表敬訪問しました。
表敬訪問では、山谷社長が、「12チーム中4位以内に入れば、プレーオフに進出できます。まずは4位以内に入ることが目標です。昨シーズンも負けた試合や引き分けた試合で勝っていれば4位以内に入っていました。今シーズンはしっかりとチームの地力をつけて、最後の20分の接戦を制することができるチームになるよう、頑張ります」と抱負を語りました。長谷川市長は、「プレーオフに出場できるよう、私も応援しています。勝つことでお客さんも増えてきて、ラグビーを知らない人にもブルーレヴズの名前が知られるようになると思います。大変なことだとは思いますが、ぜひ頑張ってください」と激励しました。
同社とは、スポーツを通じた地域活性化を図ることを目的に、令和4年8月にパートナー協定を締結し、市内小学校・こども園などでのラグビー教室の実施やスポーツ講座の講師として育成スタッフを招くなどさまざまな連携事業を行っています。この度、同チームが、市との連携をより一層深めるため、チームとして「きくがわ応援大使」に就任してくださることとなりました。
「きくがわ応援大使」とは、関係人口の創出・拡大を目的に市が昨年8月から開始した事業で、居住地に関わらず、それぞれの得意分野で自分らしく菊川推しを発信する「自治体ファンクラブ」制度です。これまでも全国から菊川市に思いを寄せる多くの人が大使に就任していますが、プロスポーツチームの応援大使就任は、今回が初となります。11月9日には、チームを代表して矢富勇毅選手と桑野詠真選手へ、市公式マスコットキャラクター「きくのん」から任命状とオリジナル名刺が手渡されました。
「NTTJAPANRUGBYLEAGUEONE2023-24」は12月9日(土曜日)開幕。12月17日(日曜日)には磐田市のヤマハスタジアムでブルーレヴズのホストゲームが行われます。市民の皆さん、応援よろしくお願いします!
チケットの購入は、公式サイト「レヴチケ」(外部サイトへリンク)へ!






11月11日(土曜日)菊川警察署1日オープンデー
11月11日、菊川警察署で「菊川警察署1日オープンデー」が開催されました。同署が地域住民に警察の仕事を知ってもらい、防犯意識や交通安全意識の向上を目的に行っているもの。市民およそ400人が訪れ、ステージや体験を楽しみました。
警察署南側駐車場では、県警音楽隊とカラーガードによる演奏と踊りが披露されました。子どもに人気の楽曲とカラーガードの軽やかなダンスで、会場は大いに盛り上がりました。演奏の途中では、「振込詐欺注意」「知らない電話に出ない」などの注意も呼びかけられました。
次に、交通機動隊員による白バイの模範走行が行われました。交通隊の隊員が白バイに乗り、5m感覚で並べられたパイロンの間をスラロームで走ったり、速度を落とさずに急旋回したりと、華麗なハンドルさばきをみせると、見守っていた来場者から大きな拍手が送られました。機動隊員は、「年末にかけて交通事故が増えることが予想されます。我々も危険な車両の取り締まりを強化しますが、皆さんもぜひ安全運転を心がけていただき、相互に協力して事故を無くすように心がけましょう」と来場者に向けて呼びかけました。
屋内では、鑑識体験のブースが設けられました。参加者は、指紋がつけられた空き缶に実際の鑑識作業で使う粉を耳かきのような毛玉で優しくこすりながらつけていき、指紋を浮き上がらせる体験を行いました。また、床に残された足跡に懐中電灯で光を当て、浮かび上がった靴底の模様がどれか見分ける体験も行われ、見事正解した児童には、景品がプレゼントされました。
市内から訪れた小学生の女子児童は、「とても楽しかった。白バイ隊の走行がカッコよかったです」と話していました。






11月10日(金曜日)堀之内小学校で創立150周年「誕生祭」が行われました
11月10日、堀之内小学校で「堀之内小学校創立150周年誕生祭」が行われました。創立150周年の節目をみんなでお祝いしようと開催。全校児童や地域の人、同校卒業生などおよそ450人が参加し、これまでの歴史を振り返ったり、伝統を未来へつなぐ思いを育んだりしました。あいにくの雨天だったため規模を縮小して体育館で行われました。
児童ははじめに、同校卒業生の太田順一(じゅんいち)さんから、小学生時代の様子を教えてもらいました。太田さんが、「堀之内小に入学した60年前は、児童は1,000人くらいでした」「小学生の頃はテレビもビデオもないので、遊びは外でした。缶蹴りや馬飛びなど友だちと工夫して遊んでいたので、遊びには不自由しなかったです」など、昔の遊びや学校の様子を話すと、児童からは驚きの声が上がりました。
次に、各学年の代表児童が、「未来の堀之内小や自分はどうなっていると思う?」について発表。2年生の代表児童は、「未来の学校給食は、ホテルのバイキングのようになっていると思います。何を食べるか選べるので、給食を残す人が少ないと思います。未来の私は、勉強を頑張って、学校の先生になっていると思います」と堂々と発表しました。
つづいて、児童たちに伝統を未来へつなぐ思いを育んでもらうため、榛原郡や川根本町で活躍する「赤石太鼓保存会」を招待し、和太鼓が披露されました。同会は、郷土愛をもち、伝統を引き継ぎ次世代へつなげていく活動をする有志グループです。児童は迫力ある演奏に真剣な表情で見入っていました。
最後に、児童全員で「堀之内小校歌」を歌い、「堀之内小150歳おめでとう」とお祝いの言葉を叫びました。



11月3日(金曜日)令和5年度市民交流プログラム院内体験ツアー「菊川病院で菊ッザニア!?」
11月3日、菊川市立総合病院で「令和5年度市民交流プログラム院内体験ツアー~菊川病院で菊ッザニア!?~」が開催されました。子どもたちに菊川市立総合病院のことや病院の仕事について興味をもってもらおうと同院が企画し初開催したもの。市内の小学4・5年生親子10組が、普段はなかなか見ることのできない病院内の見学をしたり、医療職が行っている業務の一部を模擬体験したりしました。
参加した児童は、医療用の服(スクラブ)に着替えた後、オリエンテーションを行いました。松本有司院長が「医療の仕事はチームワークが大切で、様々な仕事をしている人がいます。今日はそんな病院の仕事の一部を皆さんに体験してもらいます。体験をして病院の仕事に興味をもってもらって、いつか一緒にお仕事ができたらうれしいです」と参加者を激励しました。
その後、参加者は4つのグループに分かれ、6つの体験を行いました。「手術室ってどんなとこ?」の体験では、参加者が実際の手術室の中に入って見学をしました。手術室の自動ドアは壁の窪みに足を入れて開けることや手洗いをするときも足でスイッチを押して水や洗剤を出すことを教えてもらうと、児童は驚いた様子でした。手術室内では、心電図などの機器を見学したほか、本物の医療器具「腹腔鏡用鉗子」を使って異物に見立てたビーズをつまんで動かす体験や、医療用の針と糸で人体に見立てたスポンジを縫合する体験を行いました。
内視鏡室では、内視鏡を使って異物に見立てた飴やおせんべいをつかんで取り除く体験が行われました。細かい手先の操作が要求される作業に、児童たちは悪戦苦闘していました。
ロビーでは車いす体験が行われ、児童が保護者を車いすに乗せて、障害物を避けながら安全に素早く目的地にたどり着けるか体験しました。狭い場所や段差があるところに差し掛かると、児童は慎重に車いすを押して、通行していました。
看護師の仕事に興味があると話す参加者の大柳結菜(ゆな)さんは、「手術室で行った縫合体験が面白かったです。病院にどんなお仕事があるのかよくわかりました」と話してくれました。



11月3日(金曜日)第15回みなみやま会館まつり「みんなの文化展」
11月2日から3日まで、小笠南地区コミュニティセンターで「第14回みなみやま会館まつり~みんなの文化展~」が開催されました。今年で15回目の開催となる恒例行事で、会場には、地域住民の絵画や書、手芸や工作や、認定こども園みなみこども園と小笠南小学校の全生徒の作品など300点以上の作品が集まりました。
4年ぶりに通常の規模での開催となった今回は、ステージ発表が盛大に行われ、8団体が演奏や踊りを披露しました。オープニングでは岳洋中学校吹奏楽部による演奏が披露され、J-POPやアニメのテーマ曲などみんなで楽しめる楽曲を元気よく演奏し、会場は大いに盛り上がりました。宮坂流友銭会とJA遠州夢咲舞姫隊など、コロナ禍前は毎年出演していた団体も踊りを披露し、会場からは温かい拍手が送られました。
屋内では、子ども向けのお菓子すくいが行われ、親子連れで長蛇の列ができました。お菓子がたくさん入った桶からスコップでお菓子をすくい上げるもので、子どもたちは真剣な表情で挑戦。お目当てのお菓子が取れると、大喜びしていました。また、昼休みと閉会式前には餅まきが行われ、大人から子どもまで我先にとお餅を取っていました。






11月2日(木曜日)小笠南小学校5年生児童が自分たちで収穫したお米を販売しました
11月2日、小笠南地区コミュニティセンター駐車場で、小笠南小学校5年生児童18人が自分たちで収穫したお米を販売しました。
総合学習の一環として、米作りの大変さや食の大切さを学ぶことを目的に行っているもの。児童が地元農家の協力を得ながら5月末に田植えを、9月に稲刈りを行い収穫したお米を「南のかがやき」と命名し、チラシを作るなどして購入を呼びかけていました。
会場となった小笠南地区コミュニティセンターには、販売開始前から地域住民らが集まり、列を作っていました。販売開始時間になると児童は、「こちらのレジへどうぞ~」と言いながら、3カ所に用意されたレジに、並んでいるお客さんを手際よく案内していました。また、児童3人が、お米のかぶり物をかぶった米レンジャーに仮装して、「いらっしゃいませ~」と元気よくお客さんを呼び込んでいました。1袋300g(2合分)入り150円のお米は飛ぶように売れ、30分ほどで用意した177袋が完売しました。
買いに来た人は「子どもたちの作ったお米をとても楽しみにしていました。塩おにぎりや炊き立ての白米をそのまま食べて、お米の味を楽しみたいです」と話しました。
販売会の社長を務めた浅井亮多(りょうた)さんは、「田植えや稲刈り、販売を通して経験したことを将来に活かしたいです」と話しました。



11月1日(水曜日)小笠高校3年生が選挙模擬投票を体験しました
11月1日、小笠高校で市選挙管理委員会による出前行政講座が開催されました。国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら判断し行動する主権者を育成していくことが目的。18歳を迎え選挙権を持つ同校3年生およそ170人が参加し、市選挙管理委員の説明のもと、本物の投票箱や記載台を使った「模擬投票」を体験しました。
生徒は、事前に配られた架空の選挙公報を見て、3人の候補者の中から自分が投票したいと思う施策を掲げる1人を選択し、投票しました。模擬投票の会場は、実際の投票所と同様に投票用紙交付係や投票立会人の机が設置され、生徒は、投票記載所で投票者名を記載し、本物の投票箱に投票用紙を投函しました。また、投票後には代表生徒7人が開票作業を体験。投票用紙に記載された内容を目で確認し、手作業で候補者ごと用紙を振り分け、機械に通して集計を行いました。
同委員会事務局の榑松悠(ゆたか)書記は、令和3年に行われた菊川市議会議員選挙で2万人以上が投票する中、候補者22名のうち17位で当選した人と、18位で落選した人の投票数の差がわずか5票だったことを示し「自分の1票で社会が変わらないと思わず、ぜひ今回模擬投票でやったように自分で考え、判断して、投票してほしいです」と一票の重さを生徒に伝え、投票を呼びかけました。



よくある質問と回答
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.