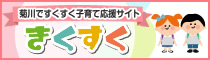ホーム > 市政情報 > ”旬感”まちのニュース > 令和4年11月まちの話題を紹介します
ここから本文です。
更新日:2022年11月19日
令和4年11月まちの話題を紹介します
11月30日(水曜日)親子「コロコロタイム」が開催されました
11月30日、小笠東地区コミュニティセンターで、親子「コロコロタイム」が開催され市内在住の未就園児親子8組が参加しました。
このイベントは、0歳児の親子を対象に毎月1回、子育ての情報交換の場をつくることを目的におがさ子育て支援センターが開催しています。今回は、いつもは育児や家事で忙しいお母さんたちのリフレッシュも兼ねて、市内の人気ベーカリー「BakeandCakeぱふ」のパティシエ鷲山智士(さとし)さんを講師に招き、フルーツサンドイッチの作り方を教えてもらいながら、楽しい一時を過ごしました。
はじめに、参加者は安全にフルーツサンドイッチ作りが進むように、子どもを背中におんぶ紐でおんぶをして準備をしました。智士さんからフルーツサンドにはさむフルーツの配置の説明を受け、参加者は生クリームを塗ったスポンジケーキの上にイチゴやぶどうなどのフルーツを慎重にのせていきました。つづいて、フルーツをのせたスポンジケーキをもう1枚のスポンジケーキでサンドしてから、サランラップで丁寧に包み冷蔵庫で冷やしました。
その後、鷲山さんがスポンジケーキの切り方を説明。実際にスポンジケーキを切ってみると、ミカンが花、ブドウが葉となったきれいな断面に、参加者から歓声が上がりました。自分がサンドしたスポンジケーキを切った参加者は、きれいな断面を見て感激していました。でき上がったスポンジケーキは、参加者が持参した容器に入れて持ち帰りました。
講師の鷲山さんは、「育児や家事で忙しい参加者の皆さんが、おいしく食べてくれたらうれしいです」と話し、7ヶ月の日奈花(ひなか)ちゃんと参加した沢瀬夢乃(ゆめの)さんは、「フルーツサンドを初めて作って楽しかったです。自宅でも作ってみたいです」話してくれました。



11月25日(金曜日)菊川西中学校3年生が「能」を鑑賞しました
11月25日、菊川西中学校で「能」の芸術鑑賞会が行われ、3年生172人が参加しました。文化庁の文化芸術による子ども育成推進事業を活用し、生徒たちが生の「能」に触れることで伝統文化への学びを深めることが目的で開催され、能楽師の佐野登さんを招き伝統文化を学びました。
佐野さんは、スライドを使って「能」がどのような伝統文化なのかを分かりやすく解説。「能」の歴史や「「狂言」との違いなどを生徒に説明しました。次に、生徒たちは、佐野さんから「羽衣」物語の謡を教わり、全員で唱和しました。その後、代表生徒が緊張しながらも見事にうたい上げました。続いて、「能」の足拍子や表現、小鼓のたたき方などの体験が行われ、佐野さん説明の後、代表生徒が実際に足拍子や表現、小鼓をたたきました。
最後に、代表生徒が「能」の装束の着付け体験をしました。何枚もの着物を重ね、最後に能面をつけると、生徒からは歓声が上がりました。
佐野さんは、「能に触れたことが、皆さんのこれからの生きるヒントになればいいです」と話し、代表生徒は「能のことをよく理解ができました。自分で考え想像することが大切だと思いました。貴重な体験をありがとうございました」とお礼をいいました。



11月21日(月曜日)菊川東中学校で思春期講演会が開催されました
11月21日、菊川東中学校で思春期講演会「出生の喜びといのちの大切さ」が開催され、同校1年生117人が参加しました。中学1年生から3年生まで、ステップを踏んで幅広い内容を伝えていけるよう、各学年での講演会を実施予定です。今回の中学1年生への講演では、自分が育ってきた過程を知り、思春期である自分の変化の理解を深め、自他ともに大切にできる心を育てることが目的に開催され、命の大切さを学びました。
講師の菊川市立総合病院の鈴木しげ子助産師は、妊娠のしくみや胎児の成長過程についてスライドを使い説明しました。また、代表生徒による新生児の身長と体重に近い乳児人形の抱っこ体験や妊婦体験、胎児の心音体験などが行われ、生徒は赤ちゃんの重さや妊婦の大変さを実感しました。妊婦体験をした生徒は、「階段を下りる時、お腹で足元が見えなくて怖かった」「仰向けに寝るとお腹が重いけど、体を横向きにしたら少し楽になった」「靴を履くときにお腹が大きくて大変だった」などと感想を話しました。
鈴木助産師は、「皆さんが今ここにいるのは、奇跡の連続です。誰もがたった一つの命です。今日は家に帰ったら、お世話になった人たちに感謝の言葉を伝えてください」と呼びかけました。



11月19日(土曜日)ぶらり文化財散歩~家康伝説と秋葉街道をめぐる~が開催されました
11月19日、ぶらり文化財散歩~家康伝説と秋葉街道をめぐる~が開催され、市内外から440人が参加。戦国時代に徳川家康が高天神城を攻略するために築かせた「獅子ヶ鼻砦」や国指定重要文化財黒田家住宅など平川地区、嶺田地区に残る文化財や埋蔵文化財センターなどを見学しながらウォーキングを楽しみました。
おがさセントラルパークに集合した参加者は、明治安田生命保険相互会社の協力により行われた健康チェックを体験。自身の血管年齢や脳年齢などを測定していました。
ウォーキングに出発した一行は、市指定文化財の朝日神社古墳や国指定重要文化財の黒田家住宅を見学。職員が特徴などを説明すると、参加者は熱心に聞いていました。
嶺田地区内に移動した一行は、嶺田神社の南にある小さな祠の前を通りました。「史跡嶺田御殿屋敷」の看板が立っており、職員が「この場所に、徳川家康がこの辺りに鷹狩りに訪れた際に逗留した屋敷があったと言い伝えられています」と説明すると、参加者は驚きの声を上げていました。
出発からおよそ1時間後、蓮池公園に到着した一行は、北側にある「獅子ヶ鼻砦」の険しい参道を、息を切らせながら懸命に上りました。頂上では職員が解説を行い「砦の南側は当時、遠浅の湿地帯でした。家康は、東側から高天神城に向かう武田軍の補給部隊の動きをこの砦から注視していたのではないかと考えられています。今でもここから高天神城が良く見えることから、高天神城の合戦の最前線であった砦だとわかります」と、獅子ヶ鼻砦の縄張り図と徳川家康が築いた6つの砦と高天神上の位置図を使って説明しました。西側を見ると、掛川市にある「高天神城」を一望することができ、参加者は当時の合戦の風景に思いを馳せているようでした。
その後も市埋蔵文化財センターや堤城などを見学した一行は、11時15分頃から続々とセントラルパークへ帰着。最後に完歩の記念品として、埋蔵文化財センターオリジナルグッズがあたるガチャガチャを1人1回ずつ回して、缶バッヂや手拭い、獅子ヶ鼻砦の御城印や茶ラリーマンの形をした香炉といった景品を持ちかえりました。
掛川市から夫婦で参加した沢柳昌枝さんは、「こんな風に教えてもらいながら歩くことはないので、とても良かったです。よく通る道でも発見がありとても良い企画でした」と感想を話しました。












11月18日(金曜日)菊川子育て支援センターを利用する親子が消防署を見学しました
11月18日、菊川子育て支援センターを利用する親子17組35人が消防署を見学しました。施設見学を通じて消防署の仕事について学び、消防署への理解や防火意識の向上を図ることを目的に消防署が開催している恒例行事。工作車・救急車の見学や消防車の乗車体験、防火服の試着など体験しました。
工作車や救急車の見学では、署員が車両ごとに役割があることやさまざまな装備品について解説すると、親子は興味深く聞いていました。油圧資器材を持ち上げてみた親子はあまりの重さに驚いていました。
消防車の乗車体験では、署員に抱きかかえられ高い座席に座った幼児は緊張した様子でしたが、慣れてくると笑顔になり手を振っていました。また、防火服を試着した幼児は、「出動」と言いながらポーズを見せてくれました。
参加した秋澤陸翔(りくと)くんのお父さんは、「はじめて消防車を近くで見ました。特に消防車に乗ってヘリポート内をまわったことがうれしそうでした」と話してくれました。
同施設見学は、10月から2月にかけて、市内幼稚園・保育園・認定こども園・子ども会などが行っています。



11月18日(金曜日)【修学旅行特別企画】内田小学校6年生を「きくがわ応援大使」に任命!
内田小学校から修学旅行時に「菊川市をPRしたい!」といううれしい申し出をいただき、11月18日、6年生42人を「きくがわ応援大使」に任命しました。旅行先での素敵な出会いを新たな学びを願って、営業戦略課長から子どもたちへ大使専用のオリジナル名刺を贈りました。
子どもたちは、本年度、総合的な学習の時間を通して「より豊かな未来を描くために自分たちができること」を考え、市を紹介するオリジナルパンフレットを作成。修学旅行で訪れた先で作成したパンフレットと一緒に菊川茶の一煎パックと名刺を配る予定です。「市の代表として元気に魅力を伝え、ファンを獲得したい」「外国の人にも渡したい」と力強く意気込みを語ってくれました。思い出に残る楽しい旅になりますように。



11月16日(水曜日)河城小学校でお茶の手もみ教室が開催されました
11月16日、お茶の手もみ体験が河城小学校で開催されました。児童たちに市特産のお茶の製造方法やお茶づくりに関心を持ってもらうことを目的に、地域の人の協力を得て行われる恒例行事。地元の茶農家である渡辺徳雄さんや菊川茶手揉保存会を講師に招き、同校3年生47人がお茶への理解を深めました。
児童たちは、3グループに分かれ、「手もみ体験」、「色々な茶葉の観察」、「蒸し器の見学」をそれぞれ体験しました。手もみ体験では、3台のホイロで茶葉の手もみをしました。ホイロごとに茶葉の状態が違っており、「はぶるい」「回転揉み」「仕上げ揉み」と茶葉の状態に合わせた揉み方があることを学びました。児童は、茶葉の水分を出すために時間をかけて丁寧にもむことや、茶葉の状態に合わせてもみ方を変えるなどの注意点を教えてもらいながら、初めての手揉みを体験しました。色々な茶葉の観察コーナーでは、19種類の日本や外国の茶葉が並べられ、児童たちはよく観察して色や香りの違いを発見しました。蒸し器の見学では、渡辺さんが摘んできた茶葉を蒸し器に入れ、香りや見た目の変化を確認しました。
渡辺さんは、「子どもたちが実際に手もみなどの体験することで、市特産のお茶に興味をもったり、お茶づくりを理解したりすると思います。今後もお茶への理解を深めてもらうために続けていきたいです」と話しました。
体験を終えた進士友望(ゆの)さんは「手もみをする前は、茶葉が柔らかかったけど段々と乾いてかたくなってきた」と話し、大石美沙希(みさき)さんは「普段よく飲むお茶の手もみをはじめて体験して楽しかった。体験では短い時間だったけど、実際には長い時間がかかると聞いて大変だなと思いました」と感想を話してくれました。



11月11日(金曜日)加茂小学校で「防災・減災『結』プロジェクト」が開催されました
11月11日、加茂小学校で5・6年生を対象とした「防災・減災『結』プロジェクト」が開催され、同校5・6年生児童およそ150人が参加しました。災害による被害を最小限に抑えるために日頃の意識や備え、いざという時の行動に活かすことを目的に開催。東北大学災害科学国際研究所地震津波リスク評価寄附研究部門プロジェクトの保田真理(まり)防災士を講師に招き、防災や減災について学びました。
はじめに、自然災害から身を守る方法などについてスライドを使い説明。保田防災士は、「家族と一緒に安全な避難場所をハザードマップで確認することや家の家具を固定するなど普段からの備えをしてください。そして、災害時には早い避難がもっとも重要です」と話しました。また、防災や減災について書かれた大きな黄色のハンカチが児童に配布され、家族で防災を確認する時に役立ててくださいと話しました。次に、児童は6人ずつのグループに分かれ、6カ所に置かれた防災や減災についての質問に答えていくスタンプラリーゲームを行いました。その後、「今日の学習ではじめて知ったこと」「家族に伝えたいこと」「自分より下の学年の子に教えてあげたいこと」を振り返り、グループごとにまとめた結果を発表しました。
グループワークを終えた6年生の岡橋咲月(さつき)さんは、「家族で避難場所を決めたいです」、6年生の木村真綾(まあや)さんは、「食品の備蓄をしたいと思います」と災害への備えを話してくれました。



11月10日(木曜日)一般社団法人日本エレベーター協会東海支部から児童用ドッジボール市内小学校に贈呈されました
11月10日、一般社団法人日本エレベーター協会東海支部から市内小学校9校へ児童用ドッジボール合計72個を寄贈していただきました。市内小学校を代表して堀之内小学校で贈呈式が行われ、長谷川寬彦(ひろひこ)市長からの礼状を澤崎淳一(じゅんいち)校長が代読し、同協会の代表に手渡しました。
澤崎校長は、「今年チャレンジする予定の3分間で何回パスができるか競うドッジボールラリーに、いただいたボールを活用したいです。ありがとうございました」と感謝を述べました。
同協会の井上さんは、「日本エレベーター協会では11月10日を『エレベーターの日』と定めています。安全・安心な利用ができるようこれからも取り組んでいきます」と話しました。
ただいたドッジボールは、各小学校の体育の授業などで活用します。ありがとうございました。



11月9日(水曜日)菊川市ご当地アイドルが「1日消防署長」に就任
11月9日、ご当地アイドル「さっきーミルキーメロディX」さんが1日消防署長に任命され、市消防本部で委嘱式が行われました。11月9日から15日までの「令和4年秋季全国火災予防運動」期間中の防火PRの一環として実施。本年度、市消防本部は「次世代を担う若者の防火活動!」をテーマにしていることから、高校生でありながらご当地アイドルとして地域で活動をしているさっきーさんを一日消防署長に任命し、「次世代の防火リーダー」として若い世代へ防火意識の働きかけをするものです。
委嘱式では、八木消防長が「さっきーさんは幼少期からご当地アイドルとして活躍するなど『菊川市愛』にあふれた方と聞いています。地域を愛する若い世代の代表として、また、若い世代への情報発信源として、今回の事業に相応しい人材であると考え、お願いしました。大変短い時間ではありますが、当本部の消防署長として、火災予防運動をよろしくお願いします」と挨拶し、さっきーさんに委嘱状を手渡しました。1日消防署長となったさっきーさんは、「防火ポスターコンクールの作品で『大切なものを失う前に』というメッセージを見て、皆さんの大切なものを一瞬で奪う火災を少しでも減らせるように少しでも啓発活動に協力できればと思います」と意気込みを語りました。
その後、さっきーさんは、隊員が行う消防車両の点検の様子を見学。隊員を前に敬礼しました。また、その後は市内のスーパーマーケットに移動し、買い物客に「火のもとに十分気を付けてください」と呼びかけながら、クリアファイルなどの火災予防啓発品を配り、火災予防をPRしました。






11月9日(水曜日)クミアイ化学工業株式会社企業版ふるさと納税寄附金お礼状贈呈式が行われました
11月9日、市役所本庁舎で企業版ふるさと納税寄附金お礼状贈呈式が行われ、長谷川寬彦市長から、クミアイ化学工業株式会社の渡邉修(おさむ)所長にお礼状が手渡されました。ました。同社は市内に同社の生物科学研究所が所在する縁もあり、市の地方創生の取り組みにご賛同いただき今回、初めて寄附をいただくことになりました。「第2期菊川市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン&総合戦略」に位置付けられている「自然環境の保全のため地球温暖化対策実行計画の策定」に対し、10月20日に100万円を寄附いただきました。
長谷川市長は、「企業版ふるさと納税の寄附をしていただきありがとうございます。市内の小学校や中学校で農業や農薬に関する正しい知識や認識を学ぶ出前授業を行っていただくなど、今後も菊川市に力添えをお願いします」とお礼の言葉を述べました。
渡邉所長は、「今後も児童も参加ができる形の出前授業で正しい知識や安全性を伝えていくなど、自然を守っていきたいと思います」と伝えました。


11月8日(火曜日)市議会教育福祉委員会が「幼保施設の今後のあり方についての意見書」を市長に提出しました
11月8日、市議会教育福祉委員会が「市議会教育福祉委員会が幼保施設の今後のあり方についての意見書」を長谷川寬彦市長へ提出しました。
同会は、「幼保施設の現状把握と今後のあり方について」をテーマとし、担当課との勉強会や公立私立園長との意見交換会、園の視察等の調査・研究などを実施。幼保施設の今後のあり方について、同会委員から出た意見を取りまとめ、意見書を提出しました。
同会の倉部光世(みつよ)委員長は、「急激な少子化に対応するため保育環境を今まで以上に整えていく必要があると思います。意見書に対する検討結果について、議会で報告をお願いします」と話しました。
意見書を受け取った長谷川市長は、「人格が形成される大事な幼保児期に重点を置き、子育てしやすいまちをつくっていきます。いただいた意見は、議会でしっかり報告したいと思います」と話しました。



11月4日(金曜日)小笠東小学校で人権教室が開催されました
11月4日、小笠東小学校で人権教室が開催されました。命の大切さや友達や周りの人と仲良くすることの大切さ、日常のあいさつの大切さを学ぶことを目的に開催。市内小学校での開催は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1年半ぶりの開催となりました。小学1、2年生児童54人が、掛川人権擁護委員協議会菊川地区研究会の委員5人から人権について学びました。
はじめに、委員がパペットを使いながら『人権』の意味を分かりやすく説明。児童たちに、「思いやりの心」、「友だちと仲良くすること」、「命を大切にすること」の3つを伝えました。
次に、朗読劇で「にっこりの心」と「とげとげの心」がみんなの心の中にあることを演技やホワイトボードを使いながら披露し、「とげとげの心」を「にっこりの心」に変えていくことの大切さを伝えました。
最後には、児童達に「にっこりの心」をさらに体で感じてもらうため、市内でピアノ講師を務める委員による、ピアノ演奏が披露されました。児童たちは、隣に座るお友達と微笑みながら、手を叩いたり、踊ったりし、ほっこりとした雰囲気に包まれました。また、終了後には同会から児童へ人権啓発品として、人権イメージキャラクターのマスコットと、自由画帳がプレゼントされました。
同会三ツ井誠会長は「今後も、園児、児童、生徒と年齢に合わせた人権教室を考え、たくさんの子どもたちに人権の大切さを伝えていきたいです」と話しました。



11月2日(水曜日)小笠高校3年生が選挙啓発活動を行いました
11月2日、小笠高校で市選挙管理委員会による出前行政講座が開催されました。国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、判断し行動していく主権者を育成していくことが目的。18歳を迎え選挙権を手にする同校3年生およそ188人が参加し、本物の投票箱や記載台を使った「模擬投票」を体験しました。
はじめに、同委員会事務局の柿沼良書記が、選挙には市の代表を選ぶもの、衆議院参議院などの議員を選ぶものがあることなど、選挙の種類や選挙制度について説明しました。同委員会の塚本淳太書記は、「若い世代は投票率が低い傾向があります。投票方法がわからないことも原因の一つだと考えられます。ぜひ選挙に積極的に参加してもらいたいです」と生徒たちに呼びかけました。
つぎに、生徒は実際の選挙で使われる投票箱や記載台を使い、模擬投票を体験しました。つづいて、開票をしました。



11月2日(水曜日)小笠南小学校5年生児童が自分たちで収穫したお米を販売しました
11月2日、小笠南地区コミュニティセンター駐車場で、小笠南小学校5年生児童26人が自分たちで収穫したお米を販売しました。
総合学習の一環として、米作りの大変さや食の大切さを学ぶことを目的に行っているもの。児童が地元農家の協力を得ながら6月に田植えを、10月に稲刈りを行い、収穫したお米を「菊米(きくまい)」と命名し、チラシを作るなどして購入を呼びかけていました。
会場となった小笠南地区コミュニティセンターには、販売開始前から地域住民らが集まり、列を作っていました。児童は、宣伝文句「お米うまいよ~」と書かれた手作りのボードを持ったり、段ボール箱でできた宣伝用着ぐるみをかぶったりしてお客さんを呼び込んでいました。
販売が開始されると、1袋300g入り150円のお米は飛ぶように売れ、30分ほどで用意した103袋が完売しました。また、児童が作成したレシピやおまけのイラストが描かれたシールも配られました。
買いに来た人は「子どもたちの作ったお米をとても楽しみにしていました。早速、今晩の夕飯に食べてみます」と話しました。



よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.