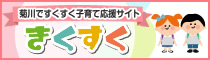ここから本文です。
更新日:2019年2月27日
野賀岐山・歴堂
教育に尽くした父と子
野賀岐山は文政7年(1824年)、高橋に生まれました。幼いころからとても勉強好きだった岐山は、母の教育を受け、紙や筆を好んでいました。10歳のとき、袴田勝彦(赤土)から国学や漢文、書を学び、※1出藍の称があったといいます。
そして、医者の山内東海(河東)につき、経史百家も学びました。昼間は農に励み、夜は学を修め、遅くまで勉強の日々。後に江戸に出て、喜多武清に絵画を教わります。
明治初期には、戸長(現在の市長)となり、さらに小学校の訓導や校長を務めました。明治21年(1888年)には高橋地区に私塾「高陽舎」を設立。子弟はおよそ千余人に及びました。話が上手な岐山が、歴史に出てくる人物の話をすると、生徒は熱中して話を聞いたそうです。
また、親に孝行を尽くし、亡き親のために毎朝の墓参りを欠かさなかったといいます。
野賀歴堂は嘉永2年(1849年)、岐山の次男として生まれました。父について学び、後に家業を継ぎます。学問に熱心に励み、詩や文、書などで特に優れていた歴堂は学校の教員になりましたが、病に倒れて故郷に帰省。静養後、静岡県師範学校に入学し、卒業しました。
※2篤学真摯の性格で、その後は、父とともに高陽舎の教諭を務めました。その傍ら、明治初期の教科書だった中国の難しい本を解説付きで書き直して刊行。十八史略や近思録などの原稿の一部も作り、辞書の編纂計画も立てました。しかしその夢もはかなく、44歳という若さで惜しくも亡くなりました。
※1弟子が師にまさること。
※2学問に熱心に励み、まじめでひたむきなこと。
(参考:わたしたちの小笠町・小笠町誌・静岡県歴史人物事典)
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.