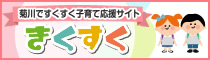ここから本文です。
更新日:2009年11月1日
松下幸作
製茶機械の普及と地方交通の先駆者
松下幸作は南山村高橋に生まれました。5歳で父を失い、さらに母とも生き別れを余儀なくされましたが、女丈夫といわれた祖母てるのもと志高く育ち、誠実で寛容な人柄は周囲の人の信望を集め、25歳の若さで小笠郡の茶業委員に選出されました。
明治20年代には、日本の茶は輸出の花形でしたが、製茶はほとんど手もみに頼っていました。先を見通す非凡な目をもっていた幸作は27歳の時、村内有志と共に共同販売組合南山社を組織し、社長となって製茶の集荷販売を行いました。この頃、現埼玉県日高市出身の高林謙三が製茶粗揉(そじゅう)機を発明し特許をとりました。幸作はさっそく高林を堀之内に招き、この機械の販売権を得て明治32年、現在地に松下工場を設立、高林式製茶機製造販売に入りました。製茶粗揉機の本格的な製造販売はわが国で初めてのことであり、地元埼玉県では「高林を静岡の堀之内にとられた」と嘆いたそうです。
幸作のもう一つの偉業は、当地方への交通(鉄道)への尽力です。幸作は川野村(現在の小笠東地区)の高力貢(こうりきみつぐ)、池新田の丸尾謙三郎と図り、堀之内~南山間に城東馬車鉄道(社長高力、取締松下)を開業しました。時に明治32年8月19日のことです。これは静岡県内で4番目、遠州では最初の民営鉄道でした。線路は堀之内停留所から西通り、五丁目を通り、ほぼ県道上を南山へ向かって伸びていました。以後、沿線に人家や商店が立ち並ぶようになり、人も農産物も運搬する鉄道は、地域に大きな役目を果たしました。
(出典:菊川町50周年記念誌「みのり」)
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.