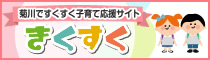ホーム > 子育て・教育 > 文化・スポーツ・生涯学習 > 社会教育 > 地域文化体験教室
ここから本文です。
更新日:2025年12月24日
地域文化体験教室
子どもたちに、自分が住む地域に伝わる文化を学ぶ機会を与えることにより、豊かな創造性を養い、あわせて他地区の子どもたちとの交流を図ることを目的として、年1回開催しています。
焼きびな絵付け体験教室を開催しました。
明治時代から、高橋地区(坊之谷)で土を焼いて人形が作られていました。その貴重な人形の型で作った猫や鳩に絵付けをして、世界でひとつだけの人形を作ってみよう。
概要
日時:令和7年12月13日土曜日10時00分〜11時30分
会場:菊川市中央公民館(菊川市下平川6225)
参加者:市内小学4〜6年生5名
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
菊川の焼きびな(坊ノ谷土人形)について
歴史
明治の初めごろ、高橋(小笠南地区)に住んでいた高木弥左衛門さんは、お米農家をしていましたが、秋の収穫が終わってから春の田植えまでの時期にできる仕事を探していました。
そこで、近くにあった宝積寺のお坊さんに助けてもらいながら、焼き物作りがさかんな三河地方(今の愛知県)から焼きびなの「型」と「作り方」を教えてもらいました。そして何回も練習して、商品として売れるような人形を作れるようになりました。
人形はひな祭りの節句人形としてとても人気が出て、一番売れた明治時代の中ごろには、東は相良や島田、西は森、袋井、磐田、遠くは水窪のあたりまでお客さんがいました。
その後、昭和の初めごろからは今のような衣装雛がはやるようになったこと、戦争が始まって色付けの材料が手に入りにくくなったことなどから、焼きびなはだんだん作られなくなっていきました。
昭和40年代に、日本各地に郷土玩具(昔から伝わるおもちゃ)の研究をしている「日本雪だるまの会」という団体の調査で、小笠の焼きびなが全国的にとても貴重なものであることがわかり、そのときに「坊ノ谷土人形」と名付けられました。現在では、高木さんの子孫にあたる高木宏さんが人形づくりを受け継いでいらっしゃいます。また、高木宏さんのお父さんに当たる高木亀次郎さんから寄贈していただいた作品が、埋蔵文化財センターどきどきで展示されています。
特徴
- 窯があった場所(坊ノ谷)の地名を取って名づけられました。
- 菊、桜、梅などの花びらやつぼみを派手に描いた、華やかな模様で色付けされています。
- 雛人形や天神人形のほか、歌舞伎の一場面を表した「歌舞伎物」、ふだんの生活や遊び、祭り等に関する「風俗物」、子どもの形をした「童子物」、福助やおかめなどの「福神」、うさぎや鳩、犬などの「動物」の人形が多いです。
(参考資料:『静岡の郷土人形』古谷哲之輔/著日本雪だるまの会/発行1996年)
よくある質問と回答
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.