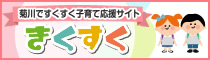ホーム > 子育て・教育 > 文化・スポーツ・生涯学習 > 文化財 > 開発行為に伴う埋蔵文化財の取り扱いについて
ここから本文です。
更新日:2025年4月22日
開発行為に伴う埋蔵文化財の取り扱いについて
概要
菊川市には、およそ3万年前の旧石器時代から近世にいたるまで多くの遺跡が確認され、現在約300ヶ所以上が確認されています。これら先人の残した遺跡は歴史や文化を明らかにする貴重な文化遺産であり、新たな文化創造への礎として大切なものです。遺跡は失われると元には戻らない貴重な国民共有の財産として文化財保護法(以下、法)で保護されています。埋蔵文化財を末永く保護・活用し子孫に伝えることは現代の私たちに課せられた責務であり、工事等を実施する開発者はその保護に協力することが求められています。
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことで、その存在が知らている土地を周知の埋蔵文化財包蔵地といいます。埋蔵文化財包蔵地は一般的には遺跡と呼ばれ、住居や溝などの生活の痕跡である遺構と、土器や石器などの遺物からなります。
埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の実施について
埋蔵文化財の所在の確認
土木工事や建築工事などで掘削作業等を伴う場合や開発を計画される際に、その工事(予定)箇所が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、次のいずれかでご確認ください。
- 菊川市内の埋蔵文化財の包蔵地の範囲は、菊川市埋蔵文化財センター(菊川市下平川618-1)で閲覧できます。
- 静岡県のホームページで、静岡県内の埋蔵文化財包蔵地の範囲を公開しています。
- 市教育委員会に直接、あるいはファックス、電話等でお問い合わせください。(電話:0537-73-1137、FAX:0537-73-1138)
- 1,000平方メートルを超える開発計画などの場合は、文書で照会してください。様式は下記リンク先からもダウンロードできます。
このほか、国・県・市指定の記念物(史跡、名勝、天然記念物)の指定地や保存地域では、法や条例等に基づき現状を変更する行為を行う際に申請等が必要な場合がありますので併せてご確認ください。
埋蔵文化財が所在する場合の手続き
文化財保護法では、埋蔵文化財包蔵地の範囲内で工事に伴う掘削作業を行う場合には、民間施工の場合は法93条第1項に基づく届出を工事着手の60日前までに、国や地方公共団体の場合は法94条第1項に基づく通知を計画策定の段階で、それぞれ市教育委員会経由で県へ書類を提出することが義務付けられています。様式は下記リンク先からもダウンロードできます。
この届出や通知に基づいて、県から工事立会いや本発掘調査の実施などの取扱いの指示が出されますが、その際に、工事による掘削が埋蔵文化財に影響を与えるかどうかを事前に確認する試掘・確認調査を市教育委員会等が行う場合もあります。
なお、本発掘調査の実施が必要との指示が出た場合には、文化財保護法の規定による諸手続きの期間や発掘調査期間などの日数がかかり工事計画に影響を与える場合もあります。開発予定地が埋蔵文化財包蔵地にかかる場合には、計画段階で市教育委員会にお問い合わせいただき、埋蔵文化財に影響が及ばない工事計画への変更等の事前調整をされることが望まれます。
埋蔵文化財が所在する場合の対応
届出や通知に対する県からの指示には次のようなものがあります。通常、書類提出後3~4週間で県から文書で回答があります。
本発掘調査
工事実施前に本発掘調査を行ってください。下の「本発掘調査の場合の手続き」を参照してください。
工事立会い
基礎掘削時などに市または県の専門職員が立会います。基礎工事の日程等が決まりましたら事前に菊川市教育委員会社会教育課にご連絡ください。
慎重工事
埋蔵文化財に影響を与えないよう、慎重に工事を実施してください。
本発掘調査を実施する場合
本発掘調査は、事業者が市教育委員会に依頼して実施することになりますが、調査の計画・準備、作業員の確保、機械による表土除去作業、人力による遺構掘り下げ作業、完掘後の図面作成や写真撮影、埋め戻しといったように現場作業だけでも日数がかかり、その後の出土遺物の整理作業や報告書作成作業も発掘調査の一連の作業となります。個々の遺跡の状況に応じて調査計画を立てることにより、具体的な期間・日程・予算などが決まってきます。
本発掘調査に要する経費は、原則として遺跡の現況を変容させる者(工事の場合は工事主体者)が負担することになります。教育委員会等の発掘主体者に本発掘調査を依頼した場合は、この依頼者が本発掘調査に要する費用の全額を負担することになります(原因者負担の原則)。なお、個人住宅等の場合は国庫等からの補助制度がありますので、お早めにご相談ください。
埋蔵文化財包蔵地外で工事中に埋蔵文化財を発見した場合
土木工事等の掘削作業中に新しく埋蔵文化財(土器や石器など)を発見した場合には、現状を変更することなく、市教育委員会を通じて県に届出・通知をすることが義務付けられています。
また、発見された埋蔵文化財の取扱いについては、遺失物法第13条により拾得物として取扱われ、文化財として認定された後、県に帰属します。
埋蔵文化財に関する問合せ
埋蔵文化財包蔵地及び周辺部での土木工事や建築工事等の掘削工事を計画される場合や、土地を造成する計画のある事業者の方は、あらかじめご相談ください。
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.